No.17[廻る命]
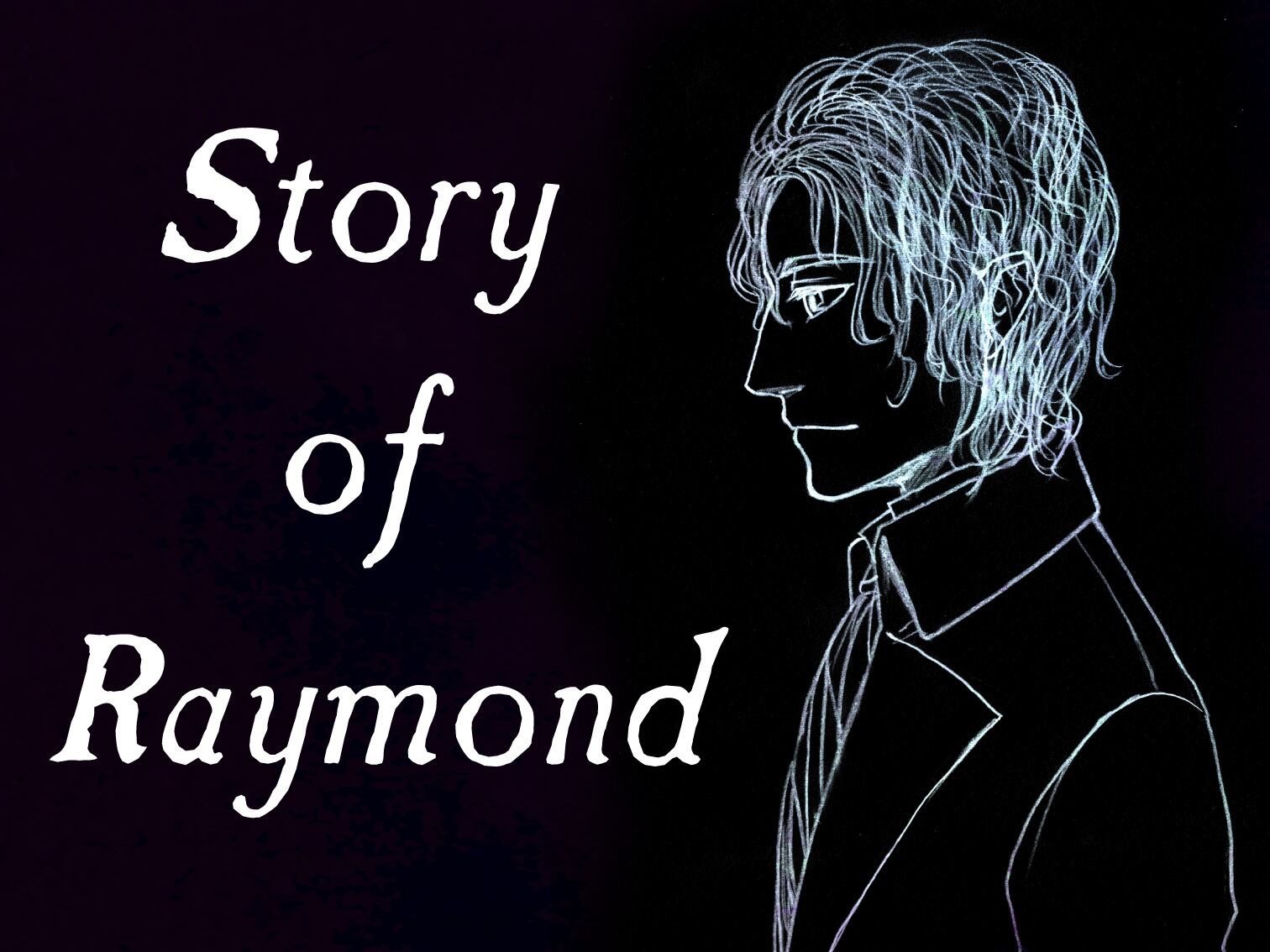

No.17[廻る命]
¥1,777
SOLD OUT
「ありがとう、レイモンドさん。
本当に助かります」
「ふふ、どういたしまして」
そう言って、庭の床扉から地下に戻る青年を見送る。
―といっても、彼は普通の青年ではない。
かすかに茶色みを帯びた白髪に、深紅の瞳を持つ彼―
ルカインは、生まれながらの吸血鬼だ。
私が住んでいる、小さな元工場の下に、彼の居住区はある。
そこで生活しやすいよう、電気を通し、地下から地上へと上がる階段を設け―
先程のやり取りに至る。
実際には、ここだけに留まらず、いくつかある地下の居住区を、彼は転々としているようだ。
普通の人間ならば、彼の外観はもちろん、[吸血鬼]と聞いただけでも驚愕するだろうが……
私は初めて遭遇した時も、全く驚きはしなかった。
というのも―
私も、特殊な生まれの人間だから。
[人間]と言えるかどうかも、分からないが……
私は、人間の父と、妖精の母を持つ混血だ。
―シトシトと雨が降り出した午後。
窓際のアンティークチェアに腰掛け、
ガラス窓に伝う雨水の向こうの、灰色の空を眺める。
今住んでいるこの小さな元工場は、私の父が昔所有していたものだ。
父は、世界を旅する冒険家―そして学者であり、
母は、とても純粋無垢な妖精だった。
二人はとても仲睦まじく、心から愛し合っていた。
私は、そんな二人が大好きだった。
だが―
ある日突然、父は何者かによって、この世から消された。
母は、父がそうなった理由を「人間界の闇を知りすぎた」と言っていた。
到底受け入れられる事ではなかった。
その時、私はすでに独立し、現在の住まいで一人暮らしていたが―
思うところがあり、遠くへと旅に出た。
訪れたのは、
静かな森の中の、半ば廃墟と化した館。
鳥のさえずりと、柔らかな陽射しが心地良い。
入り口の、重厚な木製のドアは、痛んではいるがまだ役目を果たしており―
ギギィ……と、苦しげな音を立てて開いた。
それ以外は、物音一つしない。
一階の長い廊下を、自らの足音を聞きながら進む。
その突き当たりにある、大きなガラス窓が四面を囲う一室。
部屋中に、大小様々な標本や瓶が並べられ、埃を被っている。
これは、父が生前集めていたものだ。
一つ一つ手に取り、埃を布で拭いていく。
おびただしい数の標本は、いくら拭いてもきりがない。
おまけにこの標本室は、館内に分室まである始末だ。
これらの部屋を、博物館の原型になったと言われる、Wunderkammer―[驚異の部屋]と、父が呼んでいたのも頷ける。
古びて煤がかったガラス越しに見える、暖かな陽に照らされた木々が、風に揺れ―
葉擦れの音が響き渡って、遠ざかる。
再び、静寂に包まれた。
時が止まったかのような空間。
「……………………」
側にある、瓶入りの[銀河石]を見つめる。
子供の頃、私はこれをえらく気に入っており、瓶から出しては転がして遊んでいた。
そして、その隣の[ツキヨタケ]標本を手に取る。
これは、母のお気に入りだった。
父を失った母の悲しみは深く……
家族三人で共に過ごしたこの館には、一切訪れなくなった。
ここは、両親の思い出の場所であると共に、私にとっても思い出深い場所でもある。
それが徐々に朽ち果てていくのを見るのは、とても悲しかった。
建物は、人がいなくなると―
あっと言う間に朽ちてしまうものだ。
この館を……
父の形見を、守りたい。
しかし、今の家を離れれば―
地下に住む吸血鬼の彼が、不自由する事になる。
普通の人間があの建物の所有者になれば、きっと、彼の存在を受け入れられないだろう……
そんな葛藤が続いていた時―
妖精界で、ある人物と出会った。
名前はアーネスト。
人間だが、とても陽気で、混血の私よりも妖精寄りの性格だ。
彼と親しくなるにつれ、確信できた。
アーネストが、信頼のおける人物だと。
それに……
何となく懐かしい気がして、親しみを感じていたのは―
父の面影が、彼に重なったからかもしれない。
「………………アーニー」
「?」
唐突に話し出した、隣に座る私を真っ直ぐ見つめ、続きを待つアーネスト。
遠くにそびえ立つ、妖精界特有の不思議な色合いの山々が、夕焼けに染まるのを見つめながら、話を続ける。
「………………私が今住んでいる家の、所有者になって頂けませんか?」
「ふむ。
なんだね、そんなに改まって」
私は、父と母の事、廃墟と化した館の事―
それを守るため、館に移り住みたい事を打ち明けた。
「家というより、小さな工場のような建物なんですが―
人が住まなくなると、建物はすぐに朽ちてしまいますから。
メンテナンスも兼ねて、時々足を運んで頂かなければならないですし…………」
アーネストは、ルカインの存在を受け入れてくれるだろうか。
一瞬の戸惑いの後、話す事に決めた。
「最近は、ほとんど出会わないんですが―
家の地下に位置する部屋には……
ある方が、いらっしゃる時がありましてね」
「「ある方」?」
コクリ、と頷く。
「…………吸血鬼です」
「き、吸血鬼!?
まさか……実在しているのか!」
「えぇ。
とは言っても、人間の血は吸わないと決めている、心優しい方ですよ」
「そうか……」
なぜか、こちらを見るアーネストの瞳が輝いていた。
「それでは、君の家にいれば、その吸血鬼に出会えるかもしれないのだな」
「そうなりますねぇ。
まぁ、彼には滅多に出会えませんが」
「……分かった!
私に任せたまえ」
「ありがとうございます」
そうして前居を彼に託し―
私は、森の奥の館へ移り住んだ。
こんな森の奥深く、廃墟の館には誰も近付かない。
それからはずっと、一人静かに暮らしている。
私は、生まれも特殊ながら、体質も特殊で、食事を必要としない[不食]だ。
太陽の光と水さえあれば、生きていける。
幸い、館のすぐ側には、手押しポンプ式の深井戸があり、全く不自由はない。
廃墟の館で何不自由なく過ごせるのも、この体質ゆえだ。
これも必然、か……
それから、二十何年か経っただろうか―
ある日、アーネストが、誰かを連れて訪れた。
彼が一人で時折ここを訪れる事はあったが、そんな事は初めてだ。
満面の笑みのアーネストと握手を交わす。
「お久しぶりです。[赤毛のアーニー]」
「あぁ、しばらくぶりだな!
元気にしていたかね、[灰被りのレイ]」
「………………
何度も言ってますが、その呼び方は……やめて頂きたいですねぇ。
あなたのネーミングセンスは本当に、昔から酷すぎます」
彼が連れてきた人物は三人。
一人は人間だが、他二人はネコとウサギのような妖精だ。
私達のやり取りを見てキョトンとしている人間の子に、アーネストが私を紹介する。
「彼―
レイモンドは、妖精と人間のハーフでな。
彼が妖精界に里帰りしていた時に、知り合ったのだよ」
「まぁ、大昔の話です」
人間のその子は、まだ疑問があるようで、困った表情でアーネストに問う。
「それで博士、今日はなぜ私達をここに……?」
「あぁ。実はな―
レイモンドは、君が今、白夢製作所として使用している建物の前所有者で、私は、彼からあの建物を譲り受けたのだ。
それで彼を紹介しようと思い至ったのだよ」
「そ、そうなんですか?!」
その子にニコリと笑ったアーネストが、今度は、こちらに向き直る。
「レイモンド。
君の前居は、[夢と現実の狭間にあるものを具現化]する処―
白夢製作所となった。
人間と妖精の[狭間]の君が、住んでいた場所がな。
……これも必然なのだろう。
今日はその事を報告したくて来たのだ」
そして彼は、人間の子の肩にポン、と手を置いた。
「この子が、白夢製作所所長のノア。
そして助手のイーユンとロカ君だ(^-^)」
彼らの紹介をしつつ、三人をまとめてハグするアーネスト。
人間の子は諦めてされるがままだが、助手達からはギャーギャーと苦情が飛んでいる。
その賑やかな様子に、思わず笑みを漏らしてしまった。
「助手が妖精とは。
ふふ、これはまた……奇遇ですねぇ」
「そうだろう?
彼らの出会いがまた奇遇でな。
やはり、命の廻り合わせというものを感じざるを得ないよ」
「えぇ。
私も……本当に、そう思います」
私がアーネストと出会った時にも感じた―
[命の廻り合わせ]。
幾億にも重なる、廻る命の輪で、すべての世界が廻り―
これからも連綿と続いてゆく。
だとすれば……
命は、自分だけのものではないのだろう。
私は、どんな[廻る命の輪]の一つになれるだろうか。
そんな途方もない事に思いを巡らせ―
昔の記憶にある、父の後ろ姿を思い出しながら、遠い空を見つめ……
静かに目を閉じた。


![No.1 [人生は白昼夢] No.1 [人生は白昼夢]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/c1308c02e5031ea9ba33524569aaab4e.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
![No.2 [星の種] No.2 [星の種]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/5890b1cd264f717cea10d2560a85e612.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
