No.3 [秘密のティーパーティ]
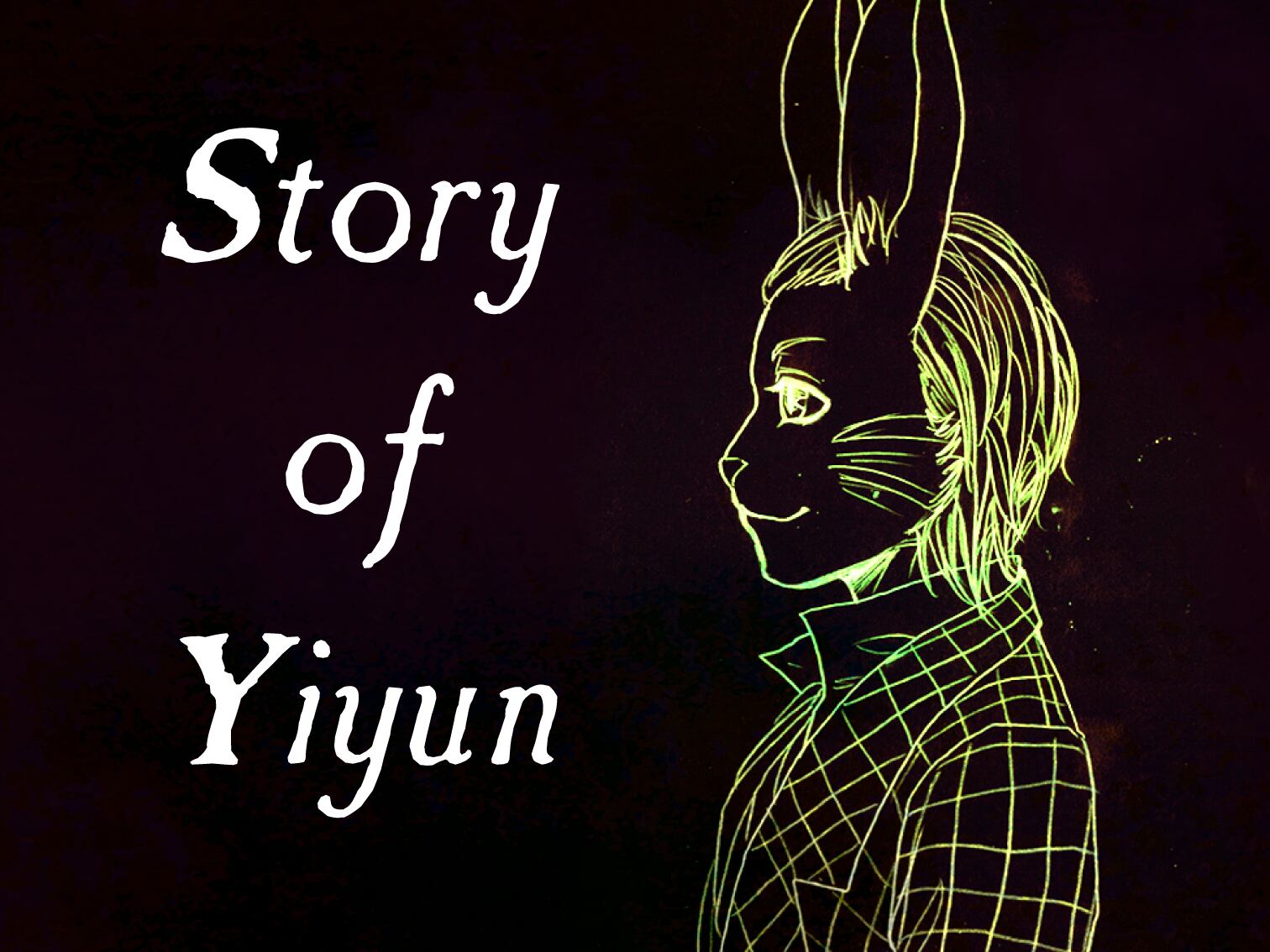

No.3 [秘密のティーパーティ]
¥333
SOLD OUT
ノアとイーユンは、時折二人だけで
[秘密のティーパーティー]を開催している。
その理由は、博士がいるとお菓子はあっという間になくなるし、ロカはハーブの匂いが苦手な為だ。
今日はそのティーパーティーの開催日。
所長のノアは結構楽しみにしているようで、朝から何となくご機嫌だ。
ティーパーティーで振る舞われる、イーユンお手製のハーブティーやお菓子もその理由の一つのようだが―
妖精界出身の彼は、お茶会の度に、妖精界にまつわる様々な話を聞かせてくれるからだ。
ティーパーティー開催場は、製作所二階、書庫の隣に位置する、ガラス張りの天井と壁にブラックアイアンの枠組みが映える、解放感溢れる広い角部屋―
いわゆるサンルームだ。
ここからは、ガーデニングが趣味の、イーユンご自慢の庭が一望できる。
午後三時の日差しが暖かい。
イーユンはこれまたご自慢のティーセットをテーブルに二人分準備し、上機嫌だ。
ノアの為に吟味した、自家製ドライハーブ等が入ったガラスポットに熱いお湯を注ぎ、すばやく蓋をする。
日の光を受けて透き通るポットの中で、茶葉や花が開き……見た目にも美しい。
ノアがそれを見つめる。
「―いつ見ても綺麗だね」
「お褒め頂き光栄です」
その様子を優しい眼差しで見ていたイーユンは、とても満足げだ。
数分後、あらかじめ暖めておいたティーカップに、丁寧にブレンドハーブティーを注ぐ。
部屋にハーブの芳香がフワリと広がった。
色とりどりの上品なお菓子も並べられ、お茶会の準備は整った。
「イーユン、いつもありがとう」
「こちらこそ、お側に置いて頂き、ありがとうございます」
二人はティーカップを持ち、お互いに向け軽く上げた。
「…美味しい」
「ふふっ、それは良かった」
ノアを真っ直ぐに見つめて微笑むイーユンは、暫しの沈黙の後―
ポツリと話し始めた。
「……まだ所長に話していませんでしたね。
なぜ、あなたの元に僕がある日突然、やってきたのかを」
遠い昔を思い出すように庭に目を遣りながら、話を続ける。
「実は……
所長が幼い子供だった頃から、僕はあなたの存在を知っていました」
「…えっ!?
イーユンがここに来たのは、数ヶ月前なのに……?」
「えぇ。
―僕が妖精界出身なのは、ご存知ですね?」
ノアがコクリと頷く。
「……元々妖精界に住んでいた僕は、人間界によく遊びに行っては見たものをいろいろ話してくる、妖精の知り合いがいました。
ある日、「面白い使命を持った人間を見つけた」と、その妖精から聞いたのです。
彼曰く、それは[夢と現実の狭間にあるものを具現化する]という人生のテーマだと。
―そう、そのテーマを持って生まれたのが所長、あなたでした」
「…!」
「僕の住んでいた妖精界も、[夢と現実の狭間にあるもの]と言える存在です。
そして、僕が持って生まれたテーマは[妖精界と人間界の架け橋になる]事でした。
―僕は何か運命を感じて、期が熟すのを、ずっと……待っていました」
ハーブティーを一口飲み、一呼吸置いたイーユンが、また話し出す。
「僕はその時、妖精界を出る事ができる年齢にまだ達していなかったので……
待っている間、その妖精に頼んでは様子を見に行ってもらい、あなたの話をいろいろ聞かせてもらいましたよ。
好きなもの、頑張っているもの、嬉しかった事、悲しかった事…………
いろんな事が、ありましたね」
彼はまるで、親が我が子の昔を懐かしむように、幸せそうに目を細めて笑う。
ティーカップを静かに置き、ノアはイーユンの話の続きを待つ。
「……そして、妖精界を出る事ができるようになり、遂に期が熟したあの日―
僕はあなたの元を訪れました。
普通は、僕のような外見の者が現れたら驚くはずなのに、所長は動じていませんでしたね」
「イーユンが来る何年か前に博士に出会って、今までの常識が通用しない存在や、世界があるのを知った後だったからね」
「ふふ、あの博士に出会った時はさぞ驚いた事でしょうね」
「確かに。本当にビックリしたよ」
少し間を置いて、イーユンがたずねた。
「僕が所長の元を訪れた時―
あなたに何と言ったか、覚えていますか?」
ノアは少しの間の後、ハッとして答えた。
「…「やっと、会えましたね」って……」
彼はニコリと笑った。
「あの時のあなたには、何の事かさっぱりだったでしょうが……
あの言葉は、心からのものでした」
席を立ったイーユンが、椅子に座っているノアに近づき、その目線に合わせるように片膝立ちになる。
「―僕は長い間ずっと、あなたに会えるのを待っていたんです」
彼は、長い指を揃えた手を自分の胸元に添え、優雅な微笑みを浮かべた。
「これからも、所長の助手をさせて頂けますか?」
「……………はい…っ」
イーユンが長い間自分を見守っていてくれた事を知り、思わず涙を溢すノア。
そんな所長の頭を、彼は、子供をあやすように優しく撫でる。
「ありがとう、本当に…」
「ふふっ、お礼を言うのは僕の方ですよ」
ハーブティーは少し冷めてしまったが―
ノアの胸の奥は、ふわりと温かくなったのだった。
[秘密のティーパーティー]を開催している。
その理由は、博士がいるとお菓子はあっという間になくなるし、ロカはハーブの匂いが苦手な為だ。
今日はそのティーパーティーの開催日。
所長のノアは結構楽しみにしているようで、朝から何となくご機嫌だ。
ティーパーティーで振る舞われる、イーユンお手製のハーブティーやお菓子もその理由の一つのようだが―
妖精界出身の彼は、お茶会の度に、妖精界にまつわる様々な話を聞かせてくれるからだ。
ティーパーティー開催場は、製作所二階、書庫の隣に位置する、ガラス張りの天井と壁にブラックアイアンの枠組みが映える、解放感溢れる広い角部屋―
いわゆるサンルームだ。
ここからは、ガーデニングが趣味の、イーユンご自慢の庭が一望できる。
午後三時の日差しが暖かい。
イーユンはこれまたご自慢のティーセットをテーブルに二人分準備し、上機嫌だ。
ノアの為に吟味した、自家製ドライハーブ等が入ったガラスポットに熱いお湯を注ぎ、すばやく蓋をする。
日の光を受けて透き通るポットの中で、茶葉や花が開き……見た目にも美しい。
ノアがそれを見つめる。
「―いつ見ても綺麗だね」
「お褒め頂き光栄です」
その様子を優しい眼差しで見ていたイーユンは、とても満足げだ。
数分後、あらかじめ暖めておいたティーカップに、丁寧にブレンドハーブティーを注ぐ。
部屋にハーブの芳香がフワリと広がった。
色とりどりの上品なお菓子も並べられ、お茶会の準備は整った。
「イーユン、いつもありがとう」
「こちらこそ、お側に置いて頂き、ありがとうございます」
二人はティーカップを持ち、お互いに向け軽く上げた。
「…美味しい」
「ふふっ、それは良かった」
ノアを真っ直ぐに見つめて微笑むイーユンは、暫しの沈黙の後―
ポツリと話し始めた。
「……まだ所長に話していませんでしたね。
なぜ、あなたの元に僕がある日突然、やってきたのかを」
遠い昔を思い出すように庭に目を遣りながら、話を続ける。
「実は……
所長が幼い子供だった頃から、僕はあなたの存在を知っていました」
「…えっ!?
イーユンがここに来たのは、数ヶ月前なのに……?」
「えぇ。
―僕が妖精界出身なのは、ご存知ですね?」
ノアがコクリと頷く。
「……元々妖精界に住んでいた僕は、人間界によく遊びに行っては見たものをいろいろ話してくる、妖精の知り合いがいました。
ある日、「面白い使命を持った人間を見つけた」と、その妖精から聞いたのです。
彼曰く、それは[夢と現実の狭間にあるものを具現化する]という人生のテーマだと。
―そう、そのテーマを持って生まれたのが所長、あなたでした」
「…!」
「僕の住んでいた妖精界も、[夢と現実の狭間にあるもの]と言える存在です。
そして、僕が持って生まれたテーマは[妖精界と人間界の架け橋になる]事でした。
―僕は何か運命を感じて、期が熟すのを、ずっと……待っていました」
ハーブティーを一口飲み、一呼吸置いたイーユンが、また話し出す。
「僕はその時、妖精界を出る事ができる年齢にまだ達していなかったので……
待っている間、その妖精に頼んでは様子を見に行ってもらい、あなたの話をいろいろ聞かせてもらいましたよ。
好きなもの、頑張っているもの、嬉しかった事、悲しかった事…………
いろんな事が、ありましたね」
彼はまるで、親が我が子の昔を懐かしむように、幸せそうに目を細めて笑う。
ティーカップを静かに置き、ノアはイーユンの話の続きを待つ。
「……そして、妖精界を出る事ができるようになり、遂に期が熟したあの日―
僕はあなたの元を訪れました。
普通は、僕のような外見の者が現れたら驚くはずなのに、所長は動じていませんでしたね」
「イーユンが来る何年か前に博士に出会って、今までの常識が通用しない存在や、世界があるのを知った後だったからね」
「ふふ、あの博士に出会った時はさぞ驚いた事でしょうね」
「確かに。本当にビックリしたよ」
少し間を置いて、イーユンがたずねた。
「僕が所長の元を訪れた時―
あなたに何と言ったか、覚えていますか?」
ノアは少しの間の後、ハッとして答えた。
「…「やっと、会えましたね」って……」
彼はニコリと笑った。
「あの時のあなたには、何の事かさっぱりだったでしょうが……
あの言葉は、心からのものでした」
席を立ったイーユンが、椅子に座っているノアに近づき、その目線に合わせるように片膝立ちになる。
「―僕は長い間ずっと、あなたに会えるのを待っていたんです」
彼は、長い指を揃えた手を自分の胸元に添え、優雅な微笑みを浮かべた。
「これからも、所長の助手をさせて頂けますか?」
「……………はい…っ」
イーユンが長い間自分を見守っていてくれた事を知り、思わず涙を溢すノア。
そんな所長の頭を、彼は、子供をあやすように優しく撫でる。
「ありがとう、本当に…」
「ふふっ、お礼を言うのは僕の方ですよ」
ハーブティーは少し冷めてしまったが―
ノアの胸の奥は、ふわりと温かくなったのだった。


![No.1 [人生は白昼夢] No.1 [人生は白昼夢]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/c1308c02e5031ea9ba33524569aaab4e.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
![No.2 [星の種] No.2 [星の種]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/5890b1cd264f717cea10d2560a85e612.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
