Another story No.1 [ノスタルジア]
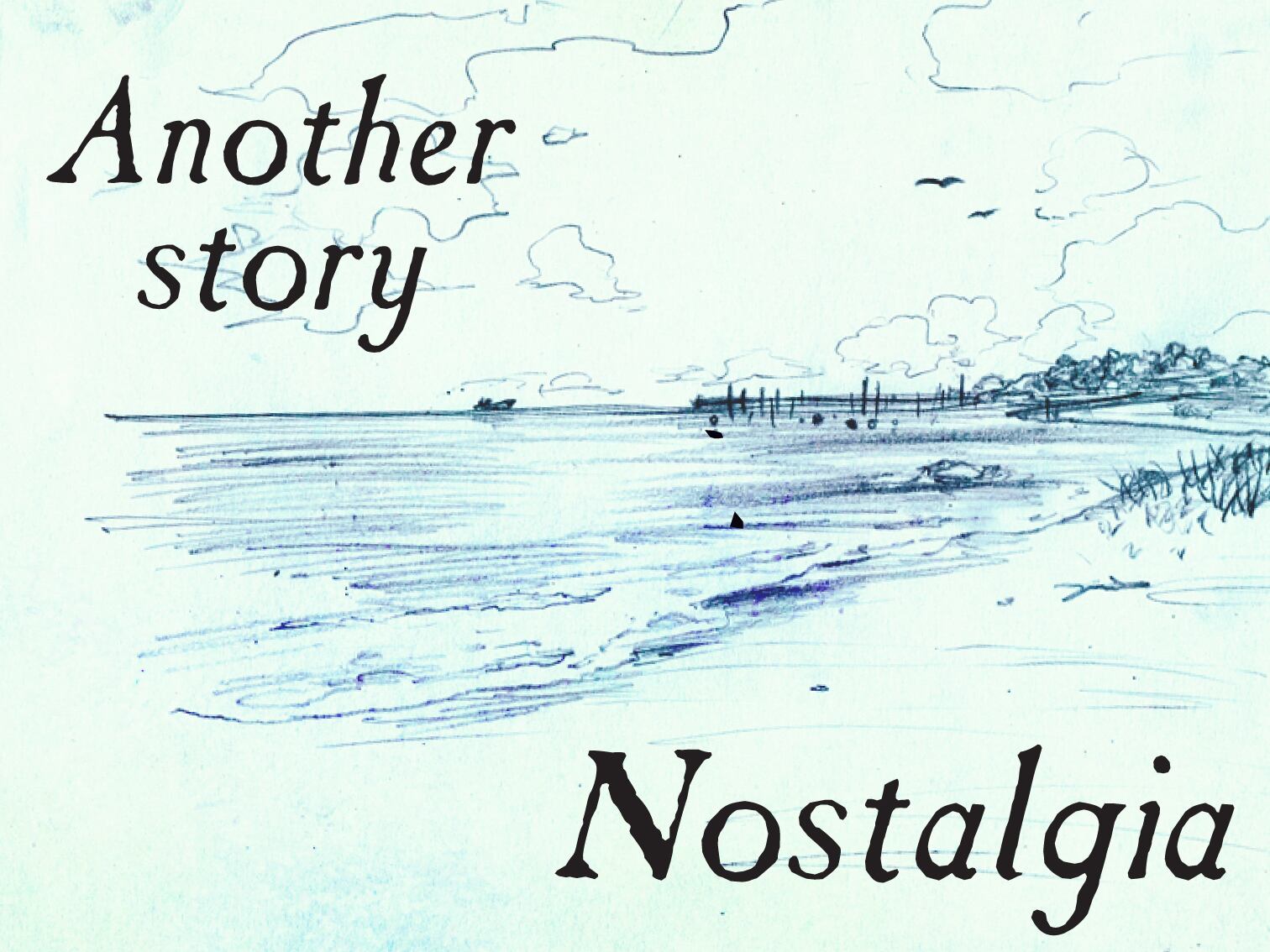
Another story No.1 [ノスタルジア]
¥111
SOLD OUT
それは、アーネスト博士と出会ったノアが、白夢製作所を開く為日々奮闘していた頃の事―
製作所の扉を勢いよく開けて、息を切らした博士が入ってきた。
「ノ、ノア……っ!!
君の、故郷が……っ
大変な事に…なっているぞ」
いつも明るい彼の緊迫したその様子に、ノアはただ事ではないと感じた。
「な、何が…あったんですか……」
博士は、ゴクリと唾を飲み―
神妙な面持ちで、小さく言葉を発した。
「き、君の、故郷は……
津波に、のまれてしまった……」
テレビなど外部の情報が分かる物を身近に置いていなかったノアは、この時―初めてそれを知った。
「………っ!」
自らの生まれ故郷に戻ろうと、すぐに身支度をし、製作所を後にしようとする。
「待ちたまえ!」
博士はそれを大声で引き留めた。
「今あちらの交通網は、完全に壊滅している。
シルフに…
私に、送らせてくれ」
アーネストの側に、光を放つ風の精が現れた。
「…行きましょう」
シルフがそう言うと、三人は風の渦に包まれた。
風の渦が止み、周りの景色が見えてくる。
「………………っ」
そこに広がる光景に、三人は絶句した。
瓦礫の山だ。
そこら中で、あり得ない物がひっくり返っている。
ここに……人の住む町があったのだろうか。
「………………」
無言で歩くノアに、博士とシルフは続いた。
―町の状態は悲惨なものだった。
ライフラインはすべて絶たれ、連絡を取る術もない。
大切な者が生きているのかすら、確かめられない。
自らの足で歩き回り、偶然にも再会を果たし、涙を流して抱き合う者―
避難所の名簿に必死に目を走らせる者―
残り僅かな食料を分け合い、何とか命を繋ぐ者達―
津波から逃げる最中、見知らぬ者にすんでの所で助けられ、生き延びた者もいたという。
すれ違った老人が言っていた。
「戦後より酷い」と。
辿り着いた先は、港町が一望できる高台だった。
ノアはその場に座り、ただその景色を眺めていた。
記憶の中の故郷とは、あまりにもかけ離れてしまったその光景は―
まるで映画のセットのようで、実感が湧いてこない。
…………何も、感じない。
だからだろう。
涙は出なかった。
「ノア………」
どう言葉を掛けていいか分からず、アーネストはその様子を見守る。
「……博士…
すみませんが……
一人に、してもらえますか」
「―あぁ、分かった。
私は、何か手助けができないか、町に行ってみるよ。
シルフを残して行くから、何かあったら……呼んでくれ」
「………はい」
博士が去った後も、ノアはただただ、町があった場所を見つめていた。
―と、側に何かが降り立つ気配がした。
見ると、一人の女性がいた。
背中に純白の翼が生えた彼女は、天使のようだった。
「……あなた、私が視えるのね」
とても優しい微笑みを浮かべ、その人物は隣に腰をおろす。
「………………」
ノアは僅かに頷き、再び町の方に視線を戻した。
その視線を追うように、彼女も同じ方向を見つめる。
「……私はメローナ。
あなたの名前も、聞いていいかしら」
「…ノア、です」
「ノアさん。素敵な名前ね」
「……………」
側にいたシルフが、メローナに話し掛けた。
「あなたも、アタシと同じ風の精ね」
「えぇ。あなたの名前は?」
「アタシはただ[シルフ]と名乗っているわ」
実は[シルフ]というのは妖精の種族名で、彼女の本当の名ではない。
名前に無頓着な妖精達の間では、種族名で名乗るというのはよくある事だ。
「そう。シルフ、どうぞよろしくね」
メローナはシルフに向かって微笑み、視線をノアに移す。
そして、ノアを後ろからそっと抱き締めた。
「っ……」
「ノアさん…
あなたの心が、泣いているわ。
………あなただけじゃない。
この町のみんな、そして、他の町のみんなも」
そう言ったメローナの瞳から涙が溢れ、ノアの肩にポタリと落ちた。
―その時やっと気付く。
自分は[悲しい]と感じている。
そして……ゆっくりと、感情が戻ってきた。
それと共に、嗚咽と涙が溢れ出す。
「……っう、く…………う…………ぇっく……」
その震える肩を、メローナはただ静かに抱き締めていた。
―しばらく泣いたノアは、落ち着きを取り戻した。
それを確認し、メローナは優しく語り掛ける。
「私―
この高台に、お店を開くわ」
「お店……ですか」
「えぇ。
私は、物から持ち主の記憶を読み解く事ができるの。
きっと、これからの…
この町のみんなの役に立てるはず。
海が見えるここから―
この町を、見守っていきたい。
お店の名前は…そうね………」
少し考え込み、彼女は再び口を開いた。
「…[el falo]」
「[エル ファロ]……
スペイン語で[灯台]。
…いい、名前ですね」
「ありがとう」
「いえ……
こちらこそ、ありがとう…ございます」
微笑みを浮かべた二人は、優しく抱き合った。
―こうして、とある港町の高台にひっそりと小さな店を開いたメローナは、今日もその町を見守っている。
皆の心が少しでも癒えるようにと、願いながら。
![No.1 [人生は白昼夢] No.1 [人生は白昼夢]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/c1308c02e5031ea9ba33524569aaab4e.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
![No.2 [星の種] No.2 [星の種]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/5890b1cd264f717cea10d2560a85e612.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
