No.14 [覗く深淵]
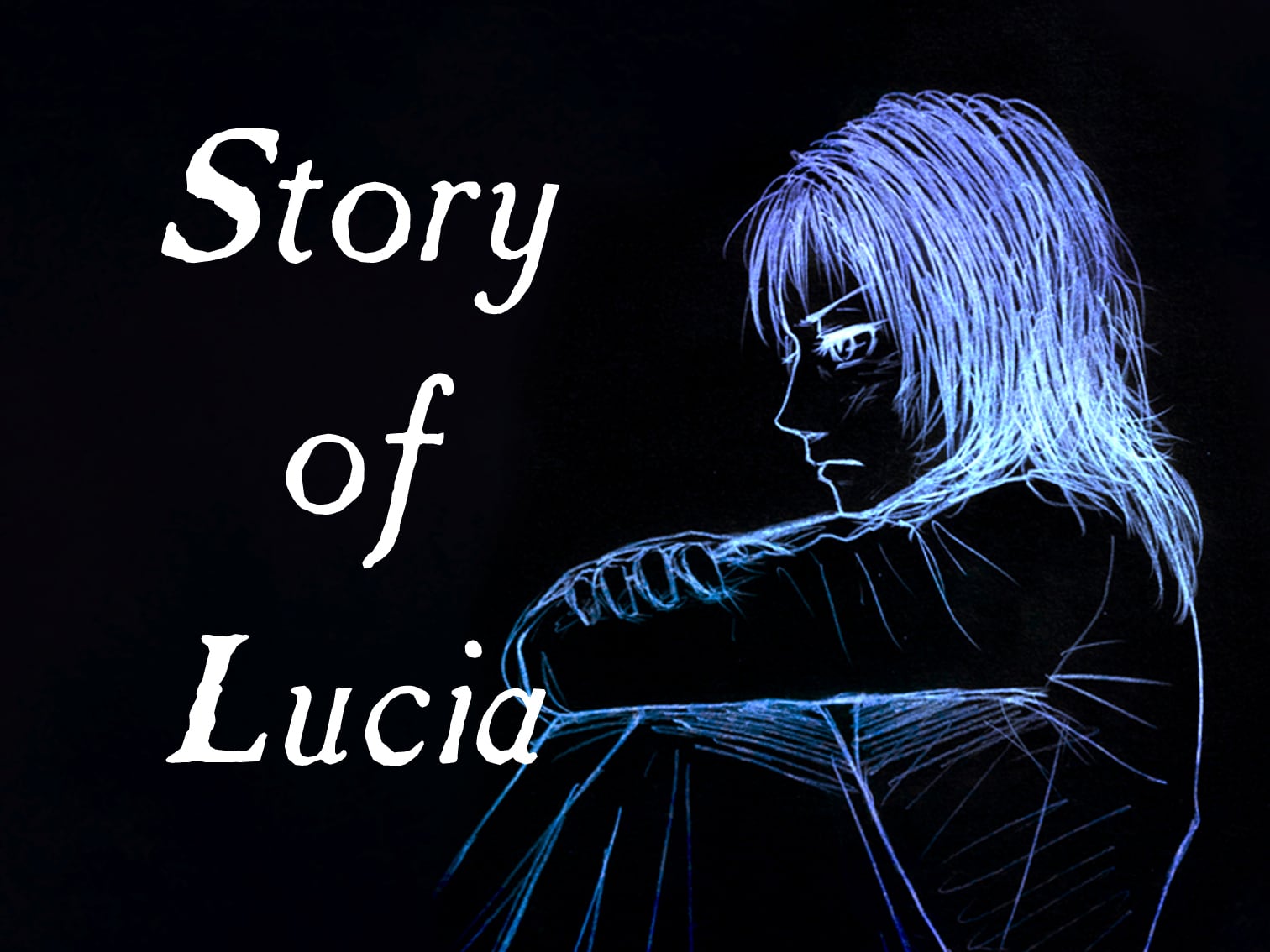


No.14 [覗く深淵]
¥1,444
SOLD OUT
―あたしの家系は、代々白魔女だった。
白魔女とは、【自然の原理を知る】者。
植物や言霊等を使って、傷付いた人々を癒す存在。
悪魔の力を使って悪行を働く黒魔女とは、同じ魔女でも全く性質が違う。
前者は【他者を癒す】為……
後者は【己の欲望】の為に、魔術を行うからだ。
でも、ずっと昔にあった【魔女狩り】は、白だろうが黒だろうが、お構いなしに処刑をしていったと聞いた。
そんな恐ろしい時代もとうに過ぎ……
今や【魔術】なんてものは、無かったもののようにされている。
本当の歴史は、権力者の手でいくらでも偽られてきたからね。
ただ―
未だ、魔女への偏見が根付いている土地があるのも事実だ。
あたしが11歳の時、母が病気で亡くなった。
祖母と祖父、父も既に戦争で亡くなっていて、残る頼りは親戚だったが……
「魔女の子供なんて気味が悪い」と拒否された。
魔女の事を詳しく知らない人間からすれば、白魔女も黒魔女も皆「異端者」でしかないんだろう。
そうして、どこにも行き場の無かった私は、深い森の中の、とある孤児院に引き取られた。
―数日後、「里親が見つかった」と連れていかれ、[ジェフリー]と名乗る男に会わされた。
……里親なんて、そんなに早く見つかるものなんだろうか。
そう思いながら、大人達のやりとりを見つめていると―
その男と、孤児院側の人間達が浮かべる満面の笑みに、不気味な違和感を感じた。
…………けれど、里親の申し出を断る理由もなかったし……
結局、あたしはそのジェフリーってやつに連れられて、孤児院を去った。
―孤児院前に停まっていた黒いワゴンに乗せられると、なぜか他にも子供が何人か乗っていた。
この子らも、孤児なのかな……
ジェフリーはよっぽど金持ちなのかもしれない。
勝手にそう解釈した。
道中、一言も言葉を交わす事なく、車はガタガタと揺れながら山道を進んでいく。
長時間の移動で眠くなり、ウトウトしはじめていた時……
車が停まった。
着いた先は、普通の家―
ではなく、なんと[お城]だった。
静かな森の中に忽然とそびえる、異様な程真っ白な外壁の城。
車から下ろされたあたしと他の子達は、その場に立ち尽くす。
「……何、ここ」
何とも言えない不自然さに、思わず言葉が漏れる。
言い知れぬ不安を感じ、他の子達と寄り添い合っていると、満面の笑みのジェフリーが、城の中に入るよう促してきた。
何だろう……
とても……嫌な予感がする…………
戸惑いながらも、入り口の前に歩み寄り、中にあたし達が全員入った直後―
城のドアが、大きな音を立てて閉じた。
「っ!?」
突然、あたしと他の子達は周りの大人達に拘束され、手足を縄で縛られた。
「何……っ、何で」
みんな抵抗して口々に声を上げたが、それを全く聞こえていないかのように無視して、大人達はあたしらを担いで城の奥へと進んだ。
薄暗く、湿気た地下へと続く螺旋状の石段を、無言で下り続ける。
「やめて!離してっ!!」
必死で暴れたが、子供の力ではどうにもならなかった。
そうして、地の底に行くんじゃないかってくらい階段を降りていった先は―
異様な空間だった。
部屋の四隅に、それぞれ大きな檻があり……
その中には、生気を失って、虚ろな目をしてうずくまる子供達が、何人もいた。
―ものすごい悪臭がする。
そして、部屋の中央には―
…………祭壇……?
周りに、何かの魔方陣が描かれて…………
「!!!」
その魔方陣を理解した瞬間、恐怖で心臓が凍りついた。
これは、悪魔崇拝の祭壇だ。
母から白魔女の知識を受け継いでいたあたしは、対極の存在である、黒魔術の魔方陣も禁忌として知っていた。
薄暗い中、床をよく見ると―
血が染み付いて、どす黒くなっている。
ここで………
悪魔への、生け贄に……
子供を―
絶望のあまり、意識を失いそうになりかけた時―
檻の中に手足を縛られたまま放り込まれた。
「っぐ」
「痛っ!」
他の子達も別の檻に放り込まれていく。
まるで物のような扱いだ。
やっと状況を理解した他の子が、声を上げ始めた。
「た……助けて…………
助けてぇーっ!!!」
中には、恐怖のあまり発狂した様子の子もいた。
「うっ……うわあぁぁっ!!!」
こんな地の底の声なんて、誰にも届かない。
不気味な程静かな地下に、助けを求める叫びだけが、虚しく響き―
消えていった。
それからは、時間の感覚、身体の感覚、感情―
すべての感覚が無くなっていった。
食事は、最低限、死なない程度与えられるのみ。
排泄物は垂れ流し。
他の子が目の前で―
生け贄として、日々悪魔に捧げられる。
言葉にする事もできない程の、おぞましい方法で……
その順番が、自分にいつ来るかも分からない。
初めは泣き叫んでいた子達も、[絶望]を目の当たりにし、希望を失っていき……
ただうずくまるようになった。
でも…………
あたしは、希望を無くしてはいなかった。
子供達が一度だけ、檻から―
地下から出されるタイミングがあった。
生け贄になる直前だ。
檻から連れて行かれ、階段を登っていき……
戻ってきた子は、儀式用の綺麗な身なりで現れる。
服は真っ白なローブだ。
あの様子だと、身体も洗っていると思う。
―逃げるチャンスがあるとすれば、そこしかない。
可能性はとても低いけど…………
何も抗わないで死ぬよりはいい。
その、僅かな希望だけを頼りに、何とか正気を保ち続けた。
―その日は突然訪れた。
檻から出されたのだ。
つまり、今日の生け贄は……あたし。
来た時と同じままの、手足を縛られた状態で、いかつい男に担がれ階段を上がっていく。
―予想通り、浴室に連れられてきた。
「………………」
隙を作る為、あえて無抵抗で生気のない様を装う。
そのお陰か―
「身体を洗え」とだけ言われ、白のローブとタオルを渡され、浴室に一人残された。
男はドアの前で待っているようだ。
置かれている石鹸で身体を洗いながら、周りを見回す。
―ダメだ、窓は鉄格子がはめられている。
唯一出入りできるのは、入ってきたあのドアだけ………
あの男の隙をついて、横をすり抜けるしかない。
一度きりのチャンス。
それが失敗したら………
あたしは………………
白いローブに、そっと袖を通す。
潰れそうな心を奮い立たせ、一息つき……
意を決して、ドアを静かに、少しだけ開けた。
男は―
携帯で誰かと話している。
今だ!!
そう思った時には、男の横を全力で走り抜けていた。
捕まえようとする手が背中をかすったが、間一髪でかわす。
「チッ!ガキが逃げたぞーっ!!」
後ろから男の叫び声が響き、どこからか他のやつらが走ってくる足音がバタバタ聞こえだした。
灰色の石造りの廊下を裸足で駆け抜ける。
「はぁ…っ、はぁ………!」
どこ………どこか………!
出られる場所……っ
迫り来る足音から逃げながら出口を探す。
廊下の窓も全部、鉄格子で塞がれている。
と、連れてこられた時に開いた、城の大きな扉に辿り着いた。
「………っく!!」
扉を閉じている大きなかんぬきを引き抜こうとしたが、重くて抜けない。
それでも、何とか少しずつ横にずり動かす。
………あと、もう少し………っ!
「!」
抜けた!!
あとは、扉さえ開けば………!
「扉を見張れーっ!」
「!!」
来る!
早く、逃げなきゃ………!
全身を使って扉を押す。
ギギ……と音を立ててゆっくり開いた隙間に、身体をねじ込む。
外が、見えた………!
「きゃあっ!!」
あと少しで身体が扉を抜けようとした時、右足をものすごい力で掴まれた。
そのまま城の中に引きずり戻される。
「このクソガキ!!
てこずらせやがって」
「嫌ぁ!!離してっ!!」
無駄な抵抗だった。
すぐに手足を縛り上げられる。
「ホントはぶん殴りてぇとこだが、生け贄を傷もんにはできねぇからな………チッ」
男はぶつくさと文句を言うが、あたしの耳には何も聞こえなかった。
もう、ダメだ………………
血の気が引いて、まるで心臓が止まったようだ。
糸の切れた、操り人形みたいになったあたしを担いで、男が地下へ続く石段を下る。
これ………
前にも、見た事ある………
あぁ………………
連れてこられた時か………
何もまともに考えられなくなっていた。
地下に辿り着き、祭壇の前に無理矢理立たされる。
司祭の格好をしてナイフを持ったジェフリーが、高らかに宣言した。
「お前を、アスタロス様への生け贄とする」
「っ!」
その宣言と同時に、魔方陣から真っ黒な煙が吹き出し、部屋のすべてを包み込む。
今までこんな事は一度も無かった。
驚きで、消えかけていた意識が一気に呼び戻される。
煙が消えると―
魔法陣の横に、深緑色のドラゴンに乗った、黒い仮面の悪魔がいた。
「あ……あぁ………っ!!
ついに…………
ア、アスタロス様が……おいでになった!!」
「……………!」
こいつが、悪魔の大公爵―アスタロス。
興奮して騒ぐジェフリーの隣で、震える手をもう片方の手で抑え、黒い仮面の奥の冷たい瞳を睨み付ける。
と、アスタロスは何が面白いのか、薄く笑みを浮かべた。
「お前は………
魔女の血を継いでいるな」
「だったら、何…………っ!」
返事をするより先に、襟を掴まれ、無理矢理ドラゴンの背に乗せられた。
「ちょ………!!」
それとほぼ同時に、魔方陣からグロテスクな姿をした悪魔達が、ぞろぞろと湧いて出てきた。
「やれ」
アスタロスがその一言を放つと―
悪魔達は、祭壇や壁を破壊しだした。
ジェフリーや他の大人達は、ひどく困惑している。
「な………何を……?!
おやめ下さい、アスタロス様………っぎゃあ!!」
「っ!」
あろうことか、悪魔達は大人達を襲い出した。
食べられている大人までいる。
恐ろしい光景に、思わず目をそらす。
そうだ、檻の中の子達を助けなきゃ………!
そう思った瞬間―
目の前の景色が靄のように消え………
次に見えたのは、月明かりが照らす森だった。
え………………
城の中じゃ、ない………!?
「なっ………」
言葉を発するより先に、悪魔とあたしを背に乗せたドラゴンは、夜空へ飛び立った。
月だけが煌々と光る雲の上、
ドラゴンは、大きな翼を上下させて、真っ直ぐ飛び続ける。
なぜか、風を切る音が全くしない。
ドラゴンの背びれをギュッと握り締め、真っ黒なマントに包まれた悪魔の背中を睨み付ける。
「………何のつもりだ、悪魔」
アスタロスはこちらを振りかえる事なく、不敵に笑い答えた。
「助けられたなら、名前くらい名乗るのが礼儀だろう」
「……………………ルシア」
あたしの名前を聞いた悪魔がククッ、と笑う。
「【ルシア】か……
「光」の意味の名を持つお前が、この世界の闇の深淵を覗くとは―
皮肉なものだな」
「…………………」
[アスタロス]という悪魔の冷酷さは、母から教わっていた。
恐怖で震える唇を噛み締め、言葉を続ける。
「……何であたしを助けた」
あたしがひるまずに言葉を発した事に驚いたのか、こちらを振り向いた悪魔は無表情になり―
そして、再び冷ややかに笑った。
「まぁ、ただの[気まぐれ]だ」
「それなら……!
他の子らも、助けてよ!!」
と、悪魔の真っ黒な仮面の奥から―
恐ろしく冷たい視線を感じた。
「勘違いするな。
悪魔に人間のような情はない。
俺は、たまたまお前を助けただけだ。
そこら辺に落ちていた石ころを「気まぐれ」で拾うようにな」
―暫しの沈黙。
少し落ち着きを取り戻し、疑問が湧いた。
「何で、あの大人達を襲わせた?
お前を崇拝してたのに」
少しの間の後、アスタロスは、若干気だるそうに言葉を返してきた。
「………質問の多い奴だな……
まぁいい。
俺は、ああいう[儀式]とやらは好きじゃない。
あんな形式ばったもの……
つまらないだろう?」
「………………っ!」
[つまらない]……?
あのおぞましい日々を、たった一言で済まされ―
腹の底から怒りが込み上げてきた。
「じゃあ、何でお前ら悪魔は人間にあんな事……
生け贄なんてさせるんだ!!」
悪魔は、一瞬呆けた表情をし―
すぐに張り付けたような笑みに戻った。
「俺達悪魔が、生け贄を望んでるって?
ククッ……ははは」
アスタロスは、額を片手で覆い、さぞ可笑しい事かのように、肩を揺らして笑う。
「―違う。
俺達の方からは、一度も生け贄など催促していない。
欲に溺れた人間達が【悪魔】の名を使って、自分達の好き放題にしているだけ……
愚かな奴らだ。
悪魔は、ただ【悪役】という役者として存在し、人間を堕落の道へ手招きする―
だが、最後にどの道を選ぶか決めるのは、お前達自身。
そうやって、悪魔は人間を試しているに過ぎない。
まぁ、己の不貞や罪を、俺達悪魔のせいにする奴は………昔からいるがな」
フン、と鼻で笑う悪魔。
よっぽど悪魔崇拝者達を嫌っているんだろう。
と、アスタロスは、またクククッ、と笑った。
「あの悪魔崇拝者達は、今頃―
魂ごと俺の手下のディナーになっている」
「っ!何で………」
「目障りだったからだ」
突き放すように一言放った後、沈黙が続いた。
「あたしを……どうするの」
その問いには答えず、アスタロスは、足でドラゴンの横腹を軽く蹴って合図を送り―
朝霧の立ち込める、湿った森に降り立った。
あたしを地上に下ろすと、悪魔はドラゴンの背中に乗ったまま、こちらを見下ろしてきた。
「人間は「死」を終わりだと思っているから、生きようと足掻くだろう?
本当はただの「過程」でしかないそれを、えらく恐れるその様と言ったら……
ははっ、滑稽極まりない」
「―あたしは【死】を恐れない。
消すのなら、今ここであたしを消せばいい」
「………………」
静かにこちらを見つめ、悪魔は言葉を続ける。
「……俺は直接人間を消す事はしない。
傍観するだけだ」
「…………」
やつが地面に降り立ち、ニヤリと笑う。
すると、ドラゴンは霧のように消えた。
「あの絶望から抜け出たお前が、これから生きる為に、どう足掻いていくのか……
見物だな」
そう言って、感情の無い笑みを浮かべた悪魔―
アスタロスは、薄暗い森の朝霧の中に、煙のように消えていった。
長い長い夢の中にいたようで、しばらく座り込む。
瑞々しい、湿った草木の匂いに包まれる。
―しばらく感じていなかった、五感の感覚が戻ってきた。
自分の両手のひらを見つめる。
あたしは、今……ここにいる…………
生きてるんだ。
両膝に手を付きながら、ヨロヨロと立ち上がり………
明るくなりはじめた森の中を、ゆっくり歩き出した。
ここは、どこなの……
どの方角に向かっているかも分からないまま、森の中、背の高い草を掻き分けて進む。
真っ白だった服はすっかり汚れ、あたしの手足に、どんどん擦り傷が増えていく。
運良く見つけた野イチゴや木の実、小川の水で飢えをしのぎながら、何日もさまよった。
自然と共存して生きていく為に、幼い頃から教わっていた―
魔女の知識が役に立った。
食べられる木の実、薬になる植物、毒のあるキノコ……
すべて覚えている。
母から教わっていたのは、それだけじゃない。
火を自力でおこす術、水をろ過する方法、土壌に合った食物の育て方……
【生きていく術】だ。
「………………」
泥で汚れた両手を、強く握りしめる。
ここがどこなのかは分からない。
でも…………
大丈夫。
あたしは……………ここで、生きていける。
その日から、[生きる]為の生活が始まった。
まずは、雨風をしのげる場所。
森を探し回った末―
今は使われていない、小さな小屋を見つける事ができた。
雨水をろ過して飲み水にする仕組みも作った。
近くに川もあるから、水には困らなさそうだ。
火も自分でおこせる。
後は―
食料を確保する為の畑作り。
でもこれは、植える[種]を見つけなきゃならない。
それに、収穫できるようになるまで時間が掛かる。
森で探しても、食材には限りがある。
何とか見つけて植えた食物は、試行錯誤して、ほんの少しずつ収穫できるようになり始めたけど……
足りてはいない。
残りは森で調達した。
それでも、食料が手に入らなくて、このまま死ぬんじゃないかって時もあった。
でも―
そういう時だけ、あの忌々しい悪魔が……
かろうじて死なない程度に、食料を置いていく。
あいつが持ってきたものなんか食べたくないけど、生きる為に食べた。
そんな事は何度もあった。
何が目的か分からない。
ただ、音も無く突然後ろに現れるし、いつも見られてる気がして―
気味が悪いったらない……
そうして何とか日々をしのぎ―
あたしは、13歳の誕生日を迎えた。
魔女にとって特別な日でもある。
魔女の家系に生まれた者が、正式に魔女になるのは、13歳の誕生日を迎えた日だからだ。
この日、正式に[白魔女]になるか[黒魔女]になるかの、誓いの儀式を行う。
あたしが選んだ道は、迷うこと無く[白魔女]だ。
儀式の準備を進めていると―
背後から嫌な気配がした。
「お前もついに魔女だな」
悪魔は、わざとらしい拍手をパチ、パチ、と打つ。
「………………」
それには反応せず、黙々と準備を続ける。
と、目の前に立ちはだかったアスタロスが、あたしの顎を片手で持ち上げ―
こちらを見据えた。
黒い仮面の奥の、血も凍るような青白い瞳と目が合う。
「………ルシア。
俺と契約を結べば―
富、名声、永遠の美貌………
この世のすべての快楽が、望むだけ手に入る。
―ただし、お前の[魂]がその対価だ。
まぁ………死んだ後の話だ、気にする事はない」
ククッと喉の奥で笑い、あたしの顎から手を離す。
あぁ、そうか………
あの日、ジェフリーの城から助け出された、あの時から―
初めから、こいつの狙いは………
これだったんだ。
[白魔女の魂は、他の魂よりも手に入りにくい分、悪魔達にとって「価値」がある。
だから狙われやすい。
くれぐれも、気を付けなさい]―
常々、母から教わっていた。
皮肉にも、あたしは【白魔女】だから悪魔に助けられ………
生き延びたのか。
白魔女のあたしを、黒魔女の道へ引き込み―
最後に魂を手にいれる………
悪魔のよくあるやり口だ。
白魔女が悪魔の誘惑と己の欲によって、黒魔女の道へ進んでしまう時もある。
逆もまた然り、黒魔女の家系に生まれながらも、欲を制して、白魔女の道に進む者もいる。
それは結局―
どの道に進むかは、生まれによって決まるんじゃなく………
最後は自分で決められるって事。
ただ、悪魔と契約した者の末路は悲惨だ。
伝説上の[ファウスト博士]が迎えた、血溜まりの中に目玉と歯だけを残して消える凄惨な結末のように。
黙り込むあたしを、面白いものでも見るかのように眺める悪魔。
もちろん、あたしの答えは決まっている。
「そんな話……乗るわけないだろう」
「ククッ、つれないな」
話を断られるのを知っていたのだろう。
全く動じない。
それどころか、アスタロスは、あっさりと手を引いた。
「今後、契約はいつでもできるからな。
―また来る」
「………………」
[また来る]―
不吉な言葉を残して、悪魔は煙のように消え去った。
その後、あたしは儀式を済ませ―
正式に[白魔女]となった。
それから、十年以上経ち―
白魔女として[一人前]と言える程にはなった。
それまでの間、あの悪魔が何度もやってきては、契約を迫ってきたけど、全く相手にはしなかった。
ただ……
[母親を生き返らせる事ができる]って言われた時は、一瞬気持ちが揺らいだけど………
すぐに正気に戻った。
死んだ者を生き返らせる事はできない。
それに、そんな悪魔の誘いなんかよりも………
せっかく身に付けた薬の知識を、誰かの為に使えない事が歯痒かった。
実は、少し離れた所に村がある。
けど、素性の知れない人間は、きっといずれ排除される……
それに―
あの森の奥の城で行われていたおぞましい儀式のメンバーは、ジェフリー達だけじゃ
なくて………世界中にいるって聞いた。
そいつらが、もしかしたら、事のすべてを知っているあたしが―
生きて逃げ延びた事を知っていて、探し回っているかもしれない。
見つかれば、どんな目に遭うか………
そう思い、近付かないでいた。
そんなある日―
森に迷い込んだ村人が、苦しそうにしながら助けを求めて、小屋に転がり込んできた。
状態を見ると………
どうやら、毒キノコを食べたみたいだ。
解毒薬を調合して飲ませたら、すぐに回復した。
「お礼はいらないよ」って、見送ったんだけど………
次の日、そいつは山盛りの果物を持ってやってきた。
それから、あたしの調合する薬が村で評判になって、時々村人が来るようになった。
初めは、ここに来ないように言ってたんだけど、
[あたしの存在は、村の人間以外には口外しない]って約束で、今は薬師として調合薬を作り、薬と生活用品を物々交換している。
―正直、あたしの薬が誰かの役に立てて………嬉しかった。
白魔女の作る調合薬は、本人が持っている[自然治癒力]を取り戻させて、結果的に症状が回復するもの。
症状を無理矢理抑えても、治る訳じゃないからね。
最後は本人の力が大事。
それは、目に見えないものも同じ話で―
村人から、パワースポットだの開運アイテムだのが流行ってるって聞いたけど………
全く、情けないったらない。
本当は、自分を癒す力も、幸せになる力も………
みんな元から備わってる。
だから、何かに[依存]する必要なんて無い。
人間の本当のパワーってのは、貰うもんじゃなくて、内から溢れてくるもの。
一番のパワースポットは、外側じゃなくて、自分の心の中……
内側にあるんだ。
なのに―
【神様】やら【天使】とやらにお願いばっかりするやつもいる。
自分が[貰う]事じゃなくて、誰かに[与える]って事は、考えないのかねぇ………
それに、そのお願いしてる相手が本当に【神様】や【天使】とは限らない。
悪魔の手口は巧妙で、そのままの姿で現れる事もあれば、神様や天使、変わり種は宇宙人なんかに化けて出てくる事もある。
本当にうまく化けるもんだから、大体の人間は見抜けないだろうけど………
やっぱり、姿を似せた所で、言葉の端々にボロが出るのさ。
その中でよく出るボロは【あなたは特別】だ。
人間じゃない存在が「あなただけは特別」だなんて言ってきたら、それは大体悪魔と見て間違いない。
「みんな特別」なのに「あなただけ」なんてのは無いからだ。
人間の虚栄心と承認欲をくすぐるのは、悪魔の常套手段だからね。
そして、嘘つきがおしゃべりなのは、人間も悪魔も同じ。
偽物は取り繕う為によくしゃべる。
ん………悪魔っていえば―
最近、アスタロスが現れなくなった。
新しい遊び相手でも見つかったのかもしれないね。
ま、あたしは平和でいいけど。
そんな事を考えながら、小屋の前の切り株に座り、木漏れ日が温かい森を眺めていたら―
誰かが、木陰から木陰へと移動しながら、ヨロヨロと歩いていた。
「………………?」
心配になり近付いてみた。
そいつは………人間じゃなかった。
でも、何なのかは知ってる。
「あんた……
吸血鬼だね?」
「!」
目を見開いてこちらを見つめ、驚いた顔であたしを凝視する吸血鬼。
「……怖く、ないのか」
「―あたしが小さい頃住んでた村の近くにも、一人吸血鬼がいてね。
吸血欲を抑える調合薬と、血の代わりに飲める飲み薬を作って渡してた」
「……そうか…………」
「待ってな。
作り方は覚えてるから」
あたしが小屋に戻ろうとすると、吸血鬼は、手のひらをこちらに向けて引き留めた。
「あぁ、いや………
今は【半吸血鬼】になっているようなんだ。
そのおかげで、吸血欲はもう無い」
「「いるようなんだ」って?
原因が分かんないの?」
「こうなる条件は知っているが………
記憶が……………無い。
気が付いたら、森の中にいて―
俺は血まみれだった。
それより前の事は………分からない。
どこから、来たのかすら……………
思い出せない」
俯いて、目をつむる吸血鬼。
本当に何も思い出せないみたいだ。
「……大変だったね。
それは、いつからなんだい?」
「………………かれこれ、三百年くらい前から、だったか………
いや、もっと経つのか」
「えぇっ!!?」
せいぜい何年かだと思っていたから、驚きで思わず声を上げた。
「あんた、三百年も森でさまよってたの!?」
「まぁ……行く宛が無かったからな」
「そ、そうか………………」
吸血鬼の風貌では、誰も助けてはくれまい。
自分が何者なのか分からないまま、何百年もさまよい続けるなんて………
想像もつかない程の孤独だっただろう。
と、吸血鬼の腕に、古い傷がある事に気付く。
「どうしたんだい、それ………」
あたしに傷を指摘され、彼はそれをなぞる。
「………分からない。
でも、何か……とても………………
とても、大切な事を………忘れてる気が、するんだ」
腕の傷を見つめる吸血鬼は、とても悲しげに見えた。
何か、力になれないかな………
「とりあえず、小屋に入りなよ」
「………ありがとう」
ふらつく吸血鬼を支えながら、小屋に戻り、椅子に座らせる。
「ちょっと、腕の傷を見るよ」
「あぁ……頼む」
「………………」
傷の周りだけ、皮膚が少しただれている。
腕の傷………
そして、記憶喪失―
昔、対吸血鬼用に使用されていた毒薬を知っている。
それが、この傷を付けた武器の先に、塗られていたんだとしたら………
「パリトキシンと、ドウモイ酸か………」
「……………?」
実は、村人から最近の薬学の本をたくさん持ってきてもらって勉強していた事もあって、毒の成分に心当たりがあった。
いくつかのハーブを調合し、湯を沸かして溶かしこんだものを差し出す。
「飲みな」
「こ、これは………?」
「記憶を呼び戻す手助けができそうなハーブを調合して、作った薬さ」
「記憶が戻るのか!?」
「………………それは分からない。
あたしの薬は、あくまでも本人の[自然治癒力]を助けるものなんだ。
あとは、あんた次第」
「………………そうか」
深緑色のそれを一気に飲み干した彼は、静かな声で「ありがとう」と礼を述べ―
力なくうなだれた。
その様子を心配そうに見つめるルシアが、口を開く。
「行くあてがないんだろ?
しばらくここにいるといいよ」
「………………いい、のか?
見ず知らずの俺を置いて………」
「いいのいいの!
あんた、悪いやつじゃないだろうし。
ちょうど人手が欲しかったんだよ。
……あたしはルシア。
あんたの名前は?」
「俺はヴァンだ。
すまん、世話になる」
人手が欲しかった、ってのは本当の事だ。
生きていく為の、日々の薪割りや畑作業の力仕事は、毎日一人でこなすのには結構な重労働だ。
男手があるととても助かる。
それから、ヴァンと生活する事になった。
昼間は太陽が照っているから、畑仕事は夜にしてくれた。
これが一番の重労働だったから、ホントに助かった。
日々を共にするうち―
だんだんと打ち解け、彼はいつしか、親友のような存在になっていった。
そして、季節が一巡りした。
今日も、薬を貰いに村人がやってきた。
いつものように、症状に合わせて薬草を調合し、手渡す。
次の日、村人がお礼として持ってきたのは、狩りに使う[弓矢]だった。
「ん~……
あたしは動物は狩らないんだけど。
まぁ、護身用で使えるかもね………」
ふと、ヴァンを見ると、様子がおかしい。
瞬きもせずに弓矢を凝視している。
息をしてないんじゃないかってくらい、微動だにしない。
「………………ヴァン?大丈夫……?」
「………………………い………だした」
「え?」
「思い、出した………………!!!」
顔を両手の平で覆い、その場にしゃがみこむヴァン。
「思い出したって………!
全部かい!?」
彼は何度も頷く。
「俺は………………
今まで、何してたんだ………
とんだバカ野郎だ……………!!」
スッと立ち上がったヴァンは、身支度を整え出した。
「行かないと」
「ヴァン!どこに行くの?!」
彼は、困ったような顔に微笑みを浮かべて、こちらを振り向いた。
「俺をずっと………
待ってる、やつの所だ。
待ってくれてるかどうかは……分からんが」
目の前に大きな右手が差し出された。
それを固く握り返す。
「今まで世話になった。
本当に、ありがとう」
「それはお互い様。
あたしも、あんたがいてくれて助かったよ。
ありがとう」
「じゃあ………」
一人去ろうと、小屋に背を向けたヴァンの肩に、ルシアが手を置いた。
「!」
「あたしも一緒に行くよ。
ちゃんと見届けないと、心配でね」
ニッと歯を見せて笑うルシアに、ヴァンも笑い返す。
「行こう」
「うん」
数日分の食料とランタンを持って、小屋を後にした。
ヴァンの待ち人が、今でも待ってくれていますように―
そう願いながら。



![No.1 [人生は白昼夢] No.1 [人生は白昼夢]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/c1308c02e5031ea9ba33524569aaab4e.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
![No.2 [星の種] No.2 [星の種]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/5890b1cd264f717cea10d2560a85e612.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
