No.11 [懺悔]
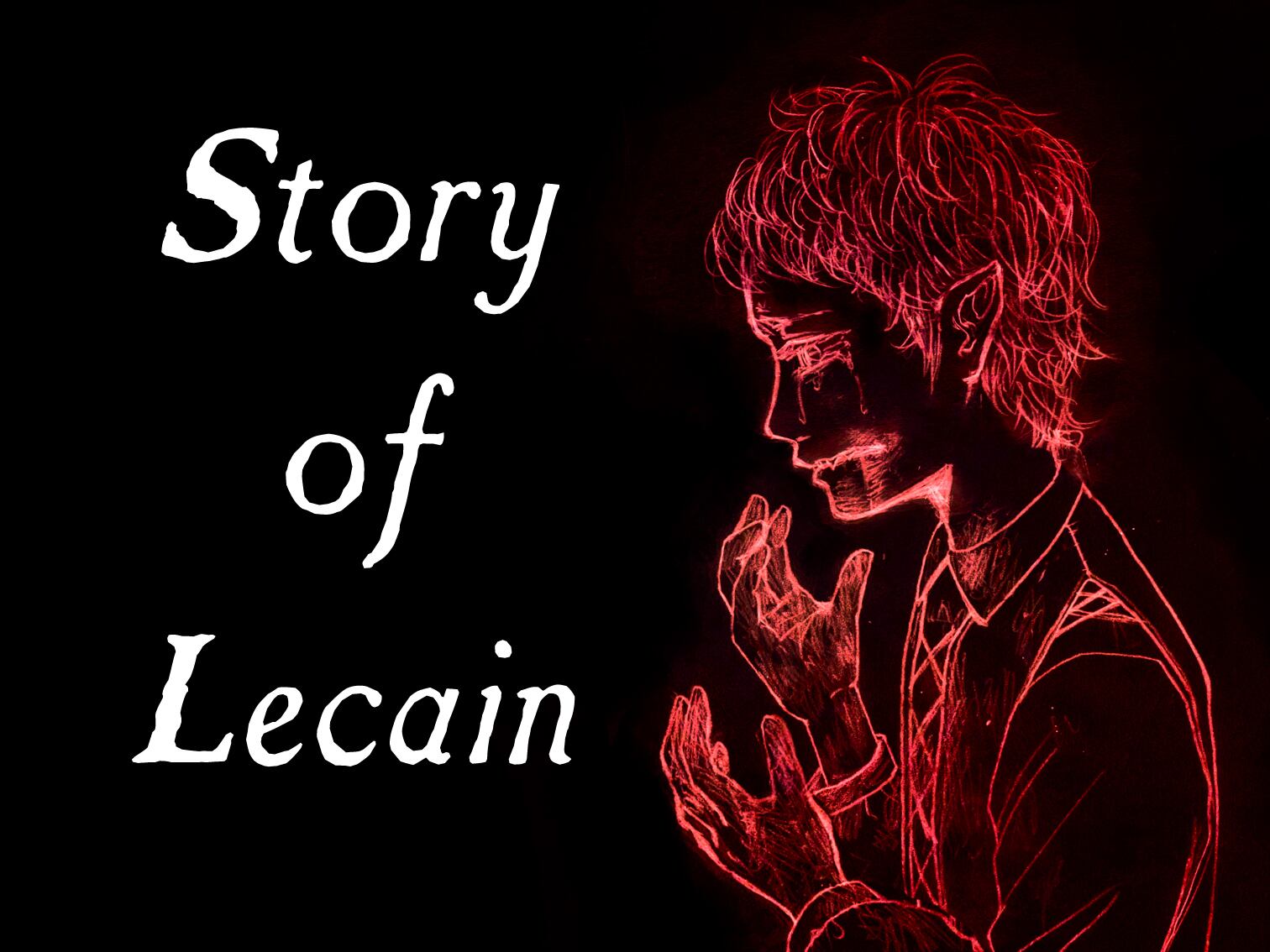
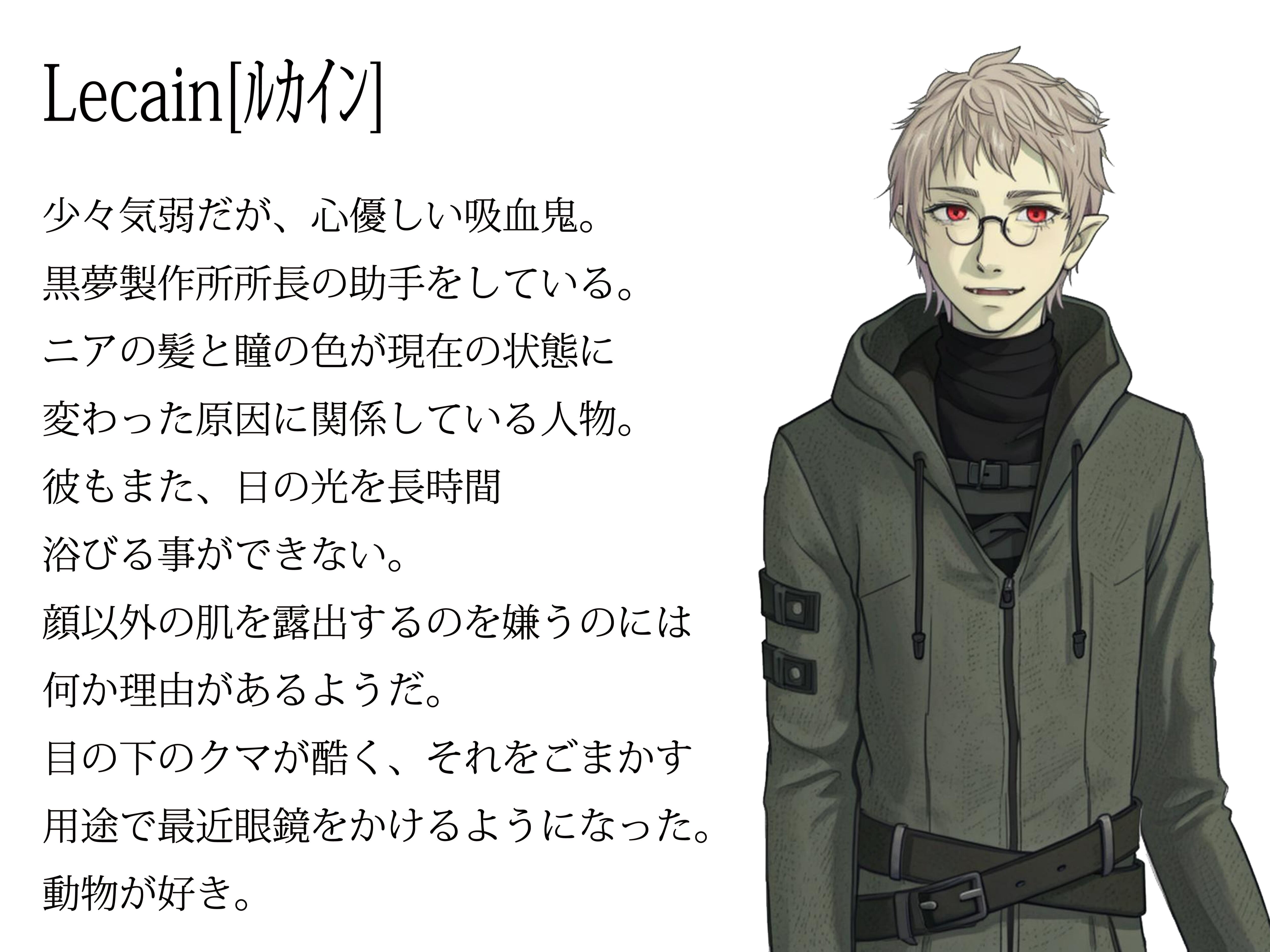
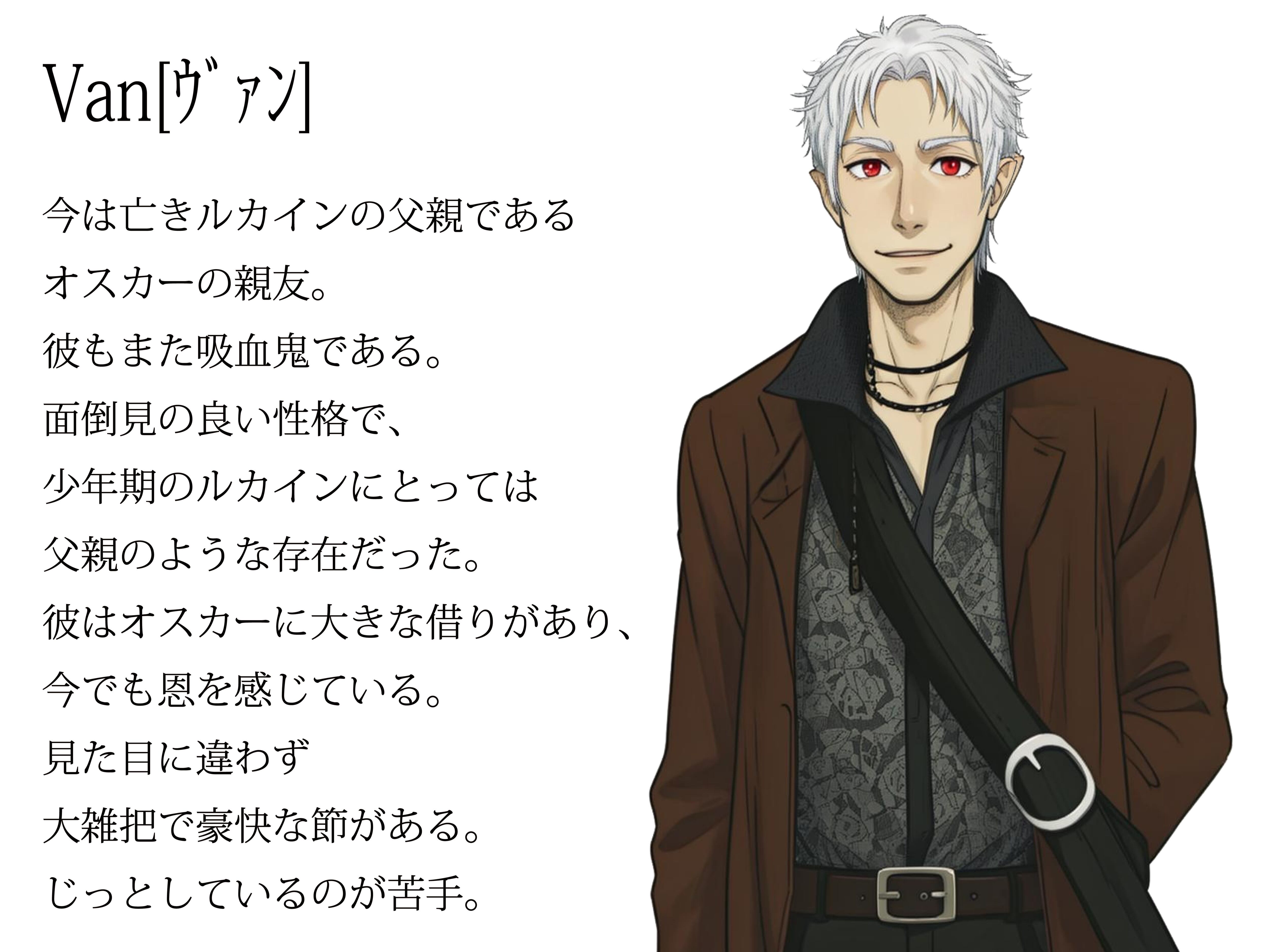
No.11 [懺悔]
¥1,111
SOLD OUT
私は幼い頃、何処にでもいるような普通の子供だった。
ある出来事が…起こるまでは―
秋の陽射しが降り注ぐその日、愛犬のエリオットを連れて森に訪れていた。
彼とは物心付いた頃からずっと一緒で、親友のような存在。
その広い森は家の裏手にあり、11歳とまだまだ子供の私が、いつも遊んでいる場所だった―
「いくぞっ、エリオット!」
僕が彫って作った木のオモチャを思い切り投げ、それをエリオットが取りに行く。
僕と彼の定番の遊びだ。
少しして、オモチャを咥えたエリオットが、千切れんばかりに尻尾を振りながら戻ってきた。
それを受け取り、わしわしと思いっきり撫でてやる。
「よぉし!もう一回だ!」
そう言ってもう一度オモチャを投げようとした時、後ろからパキッ、と音がした。
―振り向くと、そこには巨大な熊がいた。
「あ……っ」
既に逃げ切れない距離。
僕は、瞬間的に死を覚悟した。
と、僕の横をものすごい勢いで何かが走り抜けて熊に向かっていった。
エリオットだ。
「っ!行っちゃダメだ!!」
叫ぶ声を無視して、彼は自分の何倍もある獰猛な熊に勇敢に立ち向かう。
僕は恐怖のあまり、その場から動けなかった。
しばらく激しい攻防が続いたが、最終的にエリオットの気迫に負けたのか、熊はその巨体を揺らしながら、すごすごと森の奥へ消えていった。
やっと動くようになった足で、彼の元へ駆け寄る。
「エリオットっ!!」
鋭い爪に引き裂かれたその身体は、ズタズタに傷付いていた。
大量の血が滴り落ちている。
―きっと、彼は、もう……
弱って力が抜けていくエリオットを、そっと抱き抱える。
「…………僕の……
僕の、せいだ……っ」
「……………クゥ…ン」
彼は閉じかけた目で僕を見て、微かな声を上げた。
「ごめ………
ごめ、ん……………っ!!
ごめん…ね……」
そしてエリオットは、僕の腕の中で、静かに息絶えた。
「…っう、…うぐっ………」
動かなくなったその身体を、強く抱き締める。
―目の前に広がる鮮血。
僕の中に、今までに感じた事のない感覚が沸き上がる。
……何だ、この感じ―
親友同然の彼を失って悲しいはず……なのに…
僕の口は無意識に、その血に吸い寄せられる。
―気が付くと、日が落ち、辺りは薄闇に包まれていた。
視界いっぱいに、赤いものが広がっている。
―血に染まった……エリオットの毛だ。
口の中で、鉄のような味がする。
「………………え……っ」
手で口を拭うと、ベットリとした赤。
エリオットの身体には、噛み付かれたような痕が残っていた。
何で……
どういう、事………?
訳も分からず、血まみれのまま、エリオットの亡骸をただただ見つめる。
―と、遠くの方から僕の名を呼ぶ声がした。
「ルカイン!どこにいるのーっ!」
母さんだ。
ランタンの灯りがチラチラと光っている。
「か…母、さん……っ」
乾いた喉から何とか振り絞った声は届いたようで、程なくして母さんが座り込む僕を見つけた。
「ルカイ……っ!」
僕を見た母は絶句した。
「母さん……僕っ」
その言葉を遮るように、強く抱き締められる。
「…………何があったか、話して……?」
僕を抱き締める母さんの手は、震えていた。
掠れた声で、僕はゆっくりと話し出す。
熊に遭遇して襲われそうになったのを、エリオットが身を挺して助けてくれた事。
そのせいで、彼が死んでしまった事。
―僕が、エリオットの……
血を、無意識に口にした事も。
僕を見つめ、静かに話を聞いていた母さんが言った。
「……あなたの父親は……………
吸血鬼だったの」
「!!」
「でも、まさか……
子供に…遺伝するなんて………っ」
―今この時、吸血鬼というものが本当に存在している事を、初めて知った。
ましてや、それが自分の父親だなんて……
僕が物心ついた頃には、父さんはいなかった。
「父さんは病気で死んでしまったの」としか、聞かされていなかったのだ。
―僕には、吸血鬼の血が流れているというのか。
衝撃的な事が一度に起こり、思考が追い付いてこない。
「………………」
「…………エリオットに、お墓を作ってあげましょう」
母さんは、呆然とする僕の頭を優しく撫でた。
ランタンと月明かりを頼りに、木々の間、土の柔らかそうな所を見つけ、母さんと一緒に穴を掘った。
その中に、愛犬の亡骸をそっと横たわらせ、頭を撫でる。
「エリオット………っ…」
今になって涙が溢れてきた。
泣きながら、冷たくなった彼の身体に土をかけていく。
そしてその上に、彼のお気に入りだった木のオモチャを挿した。
「………………」
その簡素な墓を、しばらく見つめる。
そんな僕の背中にそっと手を添え、母さんも涙を流していた。
「この子は、命懸けであなたを守ったのよ。
―本当に、ありがとう………エリオット」
「エリオット……ありがとう………
ごめん…………っ」
僕がひとしきり泣いて落ち着いた後、母さんと一緒に、息を潜めて家に戻った。
―その時代、各地で[魔女狩り]が行われていた。
黒毛のペットを飼っていたりするだけで、使い魔を持つ[魔女]と疑われるのは勿論―
少しでもおかしな様子があれば、悪意ある隣人に「あいつは魔女だ」と告げ口され、火あぶりにされる事もあったのだ。
そうして、罪の無い人々の、たくさんの命が失われた。
神の名の元に、[悪魔]という、存在しているかすら分からないものを滅ぼすという目的を掲げた、偽りの代行者達の手によって―
独りよがりの[善]や[正義]を振りかざす狂信的な人間のする事ほど、恐ろしいものは無い。
皆が疑心暗鬼になり、怯えていた。
こんな血まみれの姿など見られようものなら、すぐに標的にされるだろう。
―幸いにも、僕達は誰にも見られる事なく家に辿り着いた。
水で濡らした布で、僕の口や手を拭いてくれる母さんを、ただぼーっと見つめ、人形のように椅子に座っていた。
その視線に気付いた母さんが、小さな声で話し始めた。
「…何から、話そうか…………」
少し考え詰めた後、言葉を続ける。
「………何が原因かは、分からないけど…
大量の血を見たのがきっかけで、ルカイン……あなたの中の、吸血鬼の本能が目覚めたのかもしれない。
もし、そうだとしたら…………」
そこで一旦話は途切れ、重い沈黙が続く。
「…………あなたは、日の光を浴びると……
死んでしまう」
「………!」
すると、母さんは僕の目の前にパンを差し出した。
「食べてみて」
「…………」
僕は受け取ったそれを少し齧る。
「…………食べた、けど…?」
そう言った直後、猛烈な吐き気に襲われた。
「……っう!」
堪らず床に吐いてしまう。
その様子を心配そうに見つめていた母さんが、微かな声で呟く。
「…………やっぱり」
悲しげな眼差しが、こちらに向けられていた。
「完全に吸血鬼になってる」
「………っ」
「さっき吐いたのは、身体が血液以外のものを栄養源として受け入れなくなって……拒否反応が出たのよ」
―それはつまり、生き物の血を飲まないと、生きていけないという事。
背筋が冷たくなるのを感じた。
「……と……父さんは……どう、してたの」
「……父さんは、森で死んだばかりの動物を探して、その血を飲むようにしていたけど……
それが見つからない時は、仕方なく……というよりも、しばらく血を飲まないでいると、その内無意識に血を求めて、気付いたら近くの動物を捕まえて……
それが死ぬまで血を吸っていた」
……僕がエリオットの血を吸った時に、似ている。
頭がクラクラしてきた。
「でも、父さんは人間の血は一度も吸わなかった」
「……動物が死ぬまで血を吸ってたんでしょ」
「仕方なかったのよ」
「…………僕はそうまでして生きたくない」
パンッ!
目を見開いた母さんは、僕の頬を平手打ちした。
「…………お願いだから……
そんな悲しい事……言わないで」
優しく抱き締められる。
母さんの匂いがした。
「父さん…オスカーは、ルカインが赤ん坊の頃に……
死んだの。
彼は、最後に言ってた。
「お前達を愛してる。俺の分まで生きてくれ」って………っ」
その当時を思い出しているのだろう。
母さんは、今までに見た事のない程悲しい顔で、涙を流していた。
[自分が吸血鬼の血を引いている]―
突然突きつけられた事実。
その後、それを身をもって知る事となる。
僕の身体は、日に日に異様な変化を見せた。
元々焦げ茶色だった髪が白に近い色になり、茶色の瞳は、鮮血のような赤になっていった。
そして犬歯は抜け落ち、代わりに鋭い牙に生え変わった。
さらには耳の先が尖り……
まるで、悪魔のような風貌だ。
こんな姿で外を出歩く訳にもいかず、フード付きのローブを纏って目深にそれを被り、日が昇っている間は、家の奥の日が差さない場所で過ごす―
そんな日々が続いた。
その日の夜、いつものように人目を忍んで、一人夜の森に来ていた。
目的は……死んで間もない動物を探す事。
母さんには、付いて来ないようにお願いしている。
僕が血をすする姿なんて、見られたくないから……
小さなランタンの灯りを頼りに、できるだけ静かに歩く。
しかし、そんなものが早々見つかるはずもなく……
気が付けば、息絶えて間もない、生暖かい小動物の血をすすっているのがほとんどだった。
その度に、僕は自分が殺めてしまった動物のお墓を作り、天国に昇れるようにと祈りを捧げた。
そして今日も、気付けば先程まで生きていた動物の血が、目の前に広がっていた。
地面にその亡骸を横たわらせて、それを見つめる。
―ポツリ、ポツリと雨が降り始めた。
暗雲で月の見えない夜空を見上げ、それを顔に受ける。
……これから一体、いくつの墓を作っていくのだろうか。
それを考えるだけで、生きる事に罪悪感を感じた。
「…………ずっと、こんな事を続けなきゃ…ならないの……?」
とその時、後ろでガサッ、と音がした。
熊かと思い素早く振り返ると、そこには男がいた。
ランタンの灯りに照らされて、血にまみれた僕の異様な姿が晒される。
「……あ…………あっ…悪魔!!
うわああぁっ!!」
叫びながら村の方に走って逃げていった。
まさか、夜の森で人に遭遇するとは考えてもみなかった僕は、唖然としていたが―
自らが置かれた状況に気付き、血の気が引いていく。
あの男が「森に悪魔がいた」と話をすれば、きっとすぐに[魔女狩り]の奴らがやってくる。
先程まで生きる事に罪悪感を感じていたというのに、いざ間近に命の危機が迫ると「死にたくない」と思った。
あの様子だと、幸い、母さんの子供だとは気付かれていない。
でも今、家に戻って気付かれてしまえば、母さんは「悪魔の母親」として、間違いなく僕と共に火あぶりにされるだろう。
―僕は、一人で逃げようと決めた。
「母さん、ごめん………
今まで…ありがとう。
どうか、元気で生きていて……」
溢れそうになる涙をこらえて、フードを被り直した僕は、雨の中―森の奥の[ある場所]を目指して進んだ。
その目的地へは、ある[目印]がある。
木の幹に貼り付けられたその小さな印は、夜にしか視認できず、もし見られても、その形状が示す意味を知らない者にとっては意味不明なものだ。
この広い森で目印がなければ、目的の場所には辿り着けない。
母さんが僕を追って来ないように、震える手でそれを取り除きながら向かった。
しばらく進み、そこに到着する。
「…………これだ」
草が生い茂る岩壁の端に隠れているそれは、一見大きいウサギ穴のようにしか見えない。
人一人が這いつくばって入るのがやっとという狭さだ。
―実は、この奥がその[ある場所]に続いている。
少し前、母さんが真夜中にこの穴の前に僕を連れて来て話してくれた。
この穴の奥の空間に、父さんが暮らしていた場所がある、と。
ここの他にもいくつか出口があって、場所は分からないが、いろんな所に繋がっているとも言っていた。
「………………」
もう、僕の事で母さんに苦労をかけたくない。
もしずっと側にいれば、いつかきっと命を失う……
会えなくなったとしても、生きていて欲しい。
万が一、母さんがここに辿り着いても追い掛けてくる事ができないよう、そこら辺の大きな石をかき集めて穴に入り、入り口を泥と石で念入りに塞いだ。
狭い横穴の先にランタンを置き、這い進んでを繰り返していくと―
突然広い空間に出た。
周りを見回す。
洞窟をそのまま住居にしたようなそこは、随分と古めかしい不思議な物や標本が並んでいる。
何とも独特な雰囲気だ。
……父さんが、集めていたんだろうか。
そういえば、ここは光の届かない穴の奥深く……
辺りの様子が確認できる明るさがある事を疑問に思い、気付いた。
何故かキャンドルに火が灯っている―
ひとつではなく、部屋の至る所に。
「……?」
それを不思議に思っていると、奥の部屋から何と人が現れた。
「わああぁっ!!?」
「っ!!?」
驚いて大声を上げた僕を見て、その人物もビクッと身を仰け反らせて声を荒げる。
「なっ、何だお前!!」
「あっ……あんたこそ誰?!
ここは、僕の父さんの隠れ家だぞ!」
それを聞いたその大柄な人物は、目を見開いて僕の顔を見たまま、ゆっくり近付いてきた。
怖くなり、思わず後ずさる。
「お前っ…………
ルカインか!」
「えっ……?」
言葉を返す間もなく、フードを取られた。
「…………あぁ、遺伝しちまったのか…」
とても小さな声で呟いたのが聞こえた。
冷静になり今気付いたが、この人物も僕と同じ赤い瞳をしている。
「あんた…
……あ、あなたも……吸血鬼…?」
「見ての通りだ」
その人がニヤリと笑って見せた口元には、鋭い牙が光っている。
「俺はヴァン。
お前の親父…オスカーのダチだったんだ。
ヨロシクな!」
「よ……よろしく、お願いします…
ヴァンさん」
「はは、そう改まんな!
呼び捨てでいいって」
そう言ってヴァンは、僕の頭をがしがしと撫でた。
何だか嬉しそうに見える。
落ち着いた僕は、今までの事、ここに来た経緯を話した。
「……そうか」
すべてを聞き終えた彼は、ただ一言そう呟いた。
ヴァンからは、吸血鬼の事についていろいろ教えてもらった。
吸血鬼は数自体がとても少なく、普段は身を隠している事もあり、同種と遭遇する確率が低くお互いを認識する事はほぼ無い。
その為、父さんとヴァンのように、吸血鬼同士が親友になるケースは極めて稀なようだ。
寿命が人間の何十倍もあるが、不死身ではなく、怪我などは普通にするし、痕も残るらしい。
致命的な傷を負えばもちろん命を落とす。
よく言われているニンニクや十字架などは何ともないが、太陽光だけが弱点で、それを浴びると数分で灰になるという。
そして……
父さんがなぜ、死んでしまったのかも聞いた。
魔女狩りをしている教団の人間達に捕まり、木にくくりつけられた状態で朝日を浴びせられ、処刑されたのだという。
母さんは赤ん坊の僕を抱いて、それを隠れて見ているしかなかった。
愛する人の、あまりにも酷い最後―
それはどんなに辛かったか……
考えると、胸が締め付けられる。
別の居住区にいたヴァンは後日、それを母さんから聞いたという。
そして「私達の事はそっとしておいて」と言われ、彼女と赤ん坊―
僕と、会う事も無くなった、と。
母さんがそう言ったのは……
ヴァンの姿を見ると、父さんを思い出して、悲しみに耐えられなくなるからだったのかもしれない。
暫しの沈黙の後、ヴァンは静かに口を開いた。
「俺はオスカーを、助けられなかった……
今でも…後悔してる。
何であの日、別の場所にいたのか……って、な。
本当に、すまない……」
僕を見つめる彼の瞳には、涙が滲んでいた。
「…ううん、ヴァンは悪くない。
悪いのは……
見境無く処刑する、魔女狩りの奴らだ」
「…………あぁ。
アイツらのした事は、絶対に許せねぇ。
俺は、神がいるかどうかは知らないが……
もしいるとしたら、そんな事はしないだろうと思う。
それこそ、人間に他の者を裁く権利なんて、ある訳無い。
…………あっていい訳が……無いんだ」
彼は握り拳を作り、険しい表情で俯く。
ヴァンによると、魔女狩りの教団の標的は、魔女だけではないという。
「…………アイツらからしたら、異教の神を崇拝する者、普通の人間とは違う能力を持つ者……
そして人間以外の存在は、すべて排除の対象なのさ。
さしずめ、俺達の事は「会話ができる猛獣」みたいな扱いだろうな。
もし見つかれば……殺される」
一呼吸置き、彼が続けた。
「俺も昔一度、奴らに見つかって殺されそうになってな……
その時に助けてくれたのが、オスカーだった。
それがきっかけでダチになった。
お前の親父は…
俺の命の恩人なんだ」
話終えたヴァンは、無骨な外見に似合わない、優しい笑みをこちらに向けた。
「ルカイン、ここに住むんだろ?」
「えっ?
………い、いいの…?ここに、いても…」
「当ったり前だ!
元々ここは、お前の親父の家だからな。
何なら俺が居候だ。だろ?」
今度は彼に似合う豪快な笑みで、ニカッと歯を見せる。
「……ふふっ、ありがとう!ヴァン」
そして僕は、彼と一緒にそこで生活を始めた。
地下の居住区や空間は、父さんが住んでいたここの他にもいくつかあり、高さがニメートル程ある地下道が分岐して、それぞれが蟻の巣のように繋がっているという。
地図を見せてもらったが、まるで地下の迷宮だ。
この居住区の各通路の入り口には、侵入者があった場合すぐ気付けるよう、鈴の付いた紐が張られている。
僕の時は、身体が小さくて紐に引っ掛からなかったから、鈴が鳴らなかったようだ。
ヴァンは「こりゃ改良が必要だな」なんて呑気にカラカラ笑っていたけど……
そして入り口の上には、チェーンで吊るされた石板があり、いざとなったらチェーンを外して入り口を閉じる事ができるようになっていた。
そんな「いざ」は無いに越した事はないが、何だって備えはあった方がいいだろう。
―ヴァンとの生活も板につき、何年か過ぎた。
僕はその日の真夜中、コンパスと地図を頼りに、昔自分が住んでいた家に一人で向かっていた。
話ができなくてもいい。
ただ、遠くからでも、母さんが生きている事を確認したかった。
と、前からこちらに向かう一つの灯りが見えた。
きっとヴァンだろう。
彼は、死後間もない動物を集めに行っていた。
―しかし近付いて分かった。
一人ではなく三人いる。
「…………っ!」
背筋が凍り、とっさに身をひるがえして逃げ出した。
その時、走る僕の横をヒュンッと何かが掠め、木に突き刺さった。
矢だ。
「この悪魔め、動くなよ」
次の矢は既にこちらに構えられている。
―この距離では逃げ切れない。
覚悟を決めたその瞬間、目の前に大きな影が現れた。
「ヴァンっ!」
「全く、お前は迷子にでもなったのか?」
その瞬間に矢が放たれ、ヴァンの腕に命中した。
「!…ってぇなぁ」
彼は一瞬痛みで顔を歪めたが、矢を引き抜くとすぐに僕を抱えて一目散に逃げ出した。
逃げる最中ヴァンは背中にも矢を受けてしまったが、その矢も乱暴に引き抜き、構わず走り続ける。
脚が早く森をよく知るヴァンは、暗闇の中魔女狩りの奴らをあっという間に引き離した。
ウサギ穴の前に着き、急いで中に入り込む。
居住区に着くなりヴァンは苦しげなうめき声を上げ、仰向けに倒れ込んだ。
「ヴァンッ!大丈夫!?」
「……ははっ、平気だ。こんなもん」
彼は強がっていたが、何やら様子がおかしい。
額に大量の汗が浮かんでいた。
もしかすると、矢の先に、毒が塗ってあったのか……
僕がその傷口に触ろうとすると、ヴァンは血相を変えてそれを制止した。
「触るな!!」
「…………それ…やっぱり、毒が……」
「どうって事ない、気にするな。
それよりも……」
荒い呼吸を繰り返す彼は、深刻な面持ちで続けた。
「……一時的に撒いたが、奴らは俺達と遭遇した地帯の森をしらみ潰しに探すだろう。
ここが見つかるのも、時間の問題だ」
ヴァンはふらつきながら、のそりと起き上がると、鍵付きの引き出しを開けてガタガタと漁り、その中にあった古びた地下通路の地図とランタン、燃料を僕に押し付けるように渡した。
「ここにはもう戻らない。別の居住区に行くぞ。
その通路だ、先に行け」
「分かった」
彼が指差した地下通路に進んで振り返った瞬間―
石板が「ゴゴォン」と大きな音を立てて閉じた。
音が一つでなかったのは、いくつかの石板を下ろしたからだ。
「ヴァンっ!!」
「……ルカイン…
お前には、絶対無事でいてほしい。
その地図の矢印通りに進め。
そうすれば……俺が住んでいた居住区に辿り着く」
「何でだよ!一緒に逃げたらいいだろ!!」
石板を力一杯押してみたが、全く動かない。
この扉はとても重く、僕一人ではビクともしない。
分厚い石板を隔てた向こう側から、くぐもったヴァンの声が聞こえた。
「俺は……
もう、大切な奴を…なくしたくないんだ。
オスカーに救われた借りを、今返す」
「僕だってヴァンが大切だよ!!
なのに、何で……!
嫌だ………こんなの……っ
嫌だよ……!!」
僕は開きもしない石板を拳で叩き続けた。
手から血が滲んでいたが、そんな事はどうでもよかった。
「……手負いの俺と一緒に逃げれば、お前が助かる確率が低い。
だから別々に逃げるんだ。
…………もし俺が生き延びたら、いつか会えるさ」
―分かっていた。
ヴァンは、死を覚悟している事を。
「絶対……
絶対、生き延びて…………
僕の所に来て……」
「…………あぁ。
お前も、意地でも生きろよ。
俺と……オスカーの分まで……な…
約束だ」
彼の声は、少し泣いているように聞こえた。
「……俺も別の通路から逃げる。早く行け!」
「…………うん…
待ってるから……っ」
僕は溢れる涙を腕で拭いながら、走ってその場を後にした。
「はぁっ、はぁ……っ…………」
途中から走る気力もなくなり、トボトボと歩きだした。
真っ暗な通路を、ランタンの灯りを頼りに歩き続ける。
―あれから、どれくらいの日数……時間が経ったのかも分からなくなっていた。
と、空気が通る音が聞こえてきた。
どうやら辿り着いたようだ。
―行き着いたその居住区は、前の所とは違った雰囲気だった。
壁や家具の配色が独特で、たくさんの本が並んでいる。
伝承録、古文書……
中には[悪魔払い]や[召喚]の方法など、変わった内容のものもあった。
―時間はいくらでもある。
僕は、そこにある本を片っ端から読破していった。
―それから、長い長い年月が流れた。
日にちを数えていない為正確ではないが、何百年か経っただろうか。
遠目にしか見ていないが……
人間社会も随分と進歩したようだ。
彼―
ヴァンが、私の元を訪れる事は無かった。
心当たりのある地域や居住区を探したりもしたが、駄目だった。
それはほぼ、彼の死を意味していた。
……それでも、私は彼を待ちたかった。
その為に生きているようなものだった。
しかし生きていくには、生き物の血が必要だ。
生きている動物から死なない程度に血を吸えればいいのだが……
それをしてしまうと、その動物は[半吸血鬼]という状態になる。
人間の半吸血鬼であれば、理性があるので血を吸う事もないだろう。
だが、本能のままに生きる彼らは話が別だ。
前に一度だけ、狐を半吸血鬼化してしまった時……
その子は、他の動物を手当たり次第噛み殺して血を求める、凶暴な怪物となった。
私は……その狐を殺めるという、苦渋の決断を下した。
仕方なかった、というのは簡単だが、その子に罪は無い。
悪いのは私……
あれは、私の罪だ。
だが、そんな事があろうとも、血を求める日々は続く。
死んだばかりの動物を見つけられず、生きている動物に手をかけてしまった日は、亡骸を埋めて冥福を祈った後―
自らの身を、戒めの意味を込め、鞭打って懺悔した。
そうして私の身体は、鞭の痕だらけになっていった。
ある晩、森で動物の死体を探していると、おばあさんがいた。
…………様子がおかしい。
近づいてみると、どうやら身体の中に悪魔が入っているらしく、一人で話していた。
何故か身体の周りが黒いもやで覆われているように見える。
こちらには気付いていないようだ。
私は試しに、悪魔払いの書で読んだ中で、自分ができそうなものを実践してみた。
心の中で呪文を唱え、相手に向かって十字を切る。
すると、彼女は話すのをやめた。
どうやら成功したようだ。
正気を取り戻したその瞳が私の姿を捉える。
が―
「ひ……!あ、悪魔っ!!」
おばあさんは、よたよたと走り去っていった。
その背中をただ見送る。
―そうか。
普通の人間からすると、私も悪魔のようなもの。
そんな私が悪魔払いの方法など覚えていて、一体何になるというのか。
「ふふ……ふはは」
ただ動物の血をすすって生き長らえる、異形の者が……人助けなど―
滑稽な自分に、一人可笑しくなり笑ってしまう。
自分がこの世に存在する意味を、最早欠片も感じなくなっていた。
私はまるで疫病神だ。
愛犬のエリオットは、私を守る為に命を失い、母に苦労をかけ、ヴァンは……
私にはもう、大切な人もいない。
失うものは何も無い。
いつか、血に飢えたあの無意識の内に、人間にまで手を出してしまうのかもしれない―
そうなる前に、この生を終わらせよう。
そう決めた私の心は、何故だか、静かな湖の水面のように穏やかだった。
―夜明け前、居住区を出て向かった先は、見晴らしの良い崖の上。
ここなら朝日を全身に浴びる事になるだろう。
吸血鬼になってから、最初で最後の日の目だ。
……もう、何かを失う心配も、傷付けることも無くなる。
とても晴れやかな気持ちだ。
その場に立ち、木々の葉擦れの音と、草木の香りの中、ただ静かに時を待つ。
―と、人の足音が聞こえた。
振り向くと、一人の少年がこちらを見て立ち尽くしていた。
彼は、生気が失われた真っ白な顔をしており、悪魔に取り憑かれた人間が纏う、独特の黒いもやが見えた。
あぁ、気の毒に……
相当苦しんだのだろう、全身痩せこけている。
せめて一時的にでも解放されればと、今すぐにできる悪魔払いを施した。
エクソシストの修行をした訳ではない私には、これが精一杯だ。
しかし無駄だと思えていた知識を、最後の最後に使う事になるとは……
こんな私でも、誰かの役に立てて良かった。
彼は少し生命力を取り戻し、会話ができるようになった。
ここに来た目的は、どうやら私と同じのようだ。
これも何かの縁かもしれないな。
彼―
ニアは、本当は生きていたいと願っていた。
しかし、悪魔の呪縛から逃れる事は、容易ではない。
私は、何とか彼を助ける方法はないかと考えた。
―そこで思い出した。
悪魔の召喚に長けていた、とある魔術師の伝記の一説だ。
それによると、悪魔は、妖精や天使等、人間以外の異形の存在に手を出す事ができないルールがあるという。
異形の存在の中には―
吸血鬼もその一種として記されていた。
彼が人間でなくなれば……
吸血鬼になれば、あるいは、悪魔から解放されるかもしれない。
私が[半吸血鬼]について知ったのは、本に挟まれていたメモを見たからだ。
父さんかヴァン……もしくは、他の誰かが書き残したものだろう。
それによると、
[吸血鬼が人間の血を致死量近くまで吸い、もしその人間が命を取りとめた場合、人間と吸血鬼の中間のような存在―半吸血鬼になる]
と記されていた。
動物だけでなく、人間も半吸血鬼化する事が分かったのはこの時だ。
他にも半吸血鬼の特性等が少し書いてあったが、真偽の程は定かではない。
しかしただ死んでしまうくらいなら、少しでも可能性のある方を選んだ方がきっといい。
今から死にゆく私が、こんな事を偉そうに言える立場でもないが……
私は、この一か八かの賭けを、ニアに提案する事にした。
―彼は、その可能性に賭ける事を決めたようだ。
人間を吸血するのはこれが初めてだ。
意を決して、その首筋に牙を立てる。
どんどん溢れ出す血を吸い続け、しばらくすると、ニアは失血により気を失った。
動かなくなった彼を、朝日が当たらない場所に横たわらせる。
―今の所、息はある。
どうか、うまくいきますように……
今生最後の朝日を浴びるべく、曙光で染まりゆく空を見上げ、夜明けを待つ。
母さん、エリオット―
本当に……ごめんなさい。
この決断を下した私を、どうか許して欲しい。
ヴァン―
「意地でも生きろ」って約束……
守れなくて、ごめん。
でもこれ以上、何かを犠牲にして生きたくはない。
いつか、人の命までをも奪ってしまう前に……
この生を終わらせる。
山の稜線から朝日が現れ、遥か頭上の空に光の道が伸びる。
―ありがとう。
私が生きる為、犠牲になってしまったすべての存在達。
これでもう、何者をも傷付ける事はない。
目を瞑り、その光を全身に浴びた。
「…………………………」
何故だろう。
朝日を浴びて数分経つというのに、まだ私はここにいる……
生きている。
目を開き、ふと自身の手を見て衝撃を受けた。
「………………?!」
まさか……!
自らに起きた変化を信じられなかった。
身体は灰にはならず、皮膚が軽い火傷のように赤くなっているだけだ。
それは、日の光に耐性がある半吸血鬼の特徴だった。
「私も…半吸血鬼化している……!」
驚きのあまり力が入らず、何とか近くの木陰に歩み入り、ゆっくりと座り込んだ。
予想外の出来事に、頭が真っ白になる。
そして徐々に、歓びの感情が沸き上がり、自然と涙が溢れていた。
「そうか……私は…
もう、血を吸わなくても、生きていけるのか……」
もう一つの半吸血鬼の特徴、それは―
[血を吸わずとも、人間と同じ食事で生命を維持できる]事。
自分は、他の命を犠牲にせずとも生きていける。
木陰で横になるニアに視線を移す。
焦げ茶色だった彼の髪は、白く染まりつつあった。
―どうやら、半吸血鬼化は成功したようだ。
良かった。本当に……
私までもが半吸血鬼になった原因は不明だが、彼のお陰である事は確かだ。
と、ニアが目覚めると共に咳き込み出す。
大丈夫だろうかと様子を伺っていると、彼の口から大量の黒い煙が吹き出した。
予想は当たっていたようで、純粋な人間では無くなったニアの身体に悪魔達が居られなくなり、出てきたのだ。
片方の悪魔は相当腹を立てており、もう片方は飄々としていた。
そして手を出せない為諦めたのか、悪魔達は去った。
朝日の満ちる静かな森の中、歓びの抱擁を交わす。
生きている事に歓びを感じたのは、何百年ぶりだろうか。
私達は、お互いが命の恩人となった。
人と人は、廻り合わせというものがあるのだな、と思わざるを得ない。
忌み嫌われる存在の、この私にも……
出来る事はあったのだ。
最後の最後で助けられ、生かされたこの命―
誰かの為……
平和の為に生かしていこうと、心から誓った。



![No.1 [人生は白昼夢] No.1 [人生は白昼夢]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/c1308c02e5031ea9ba33524569aaab4e.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
![No.2 [星の種] No.2 [星の種]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/5890b1cd264f717cea10d2560a85e612.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
