No.9 [理想の世界]
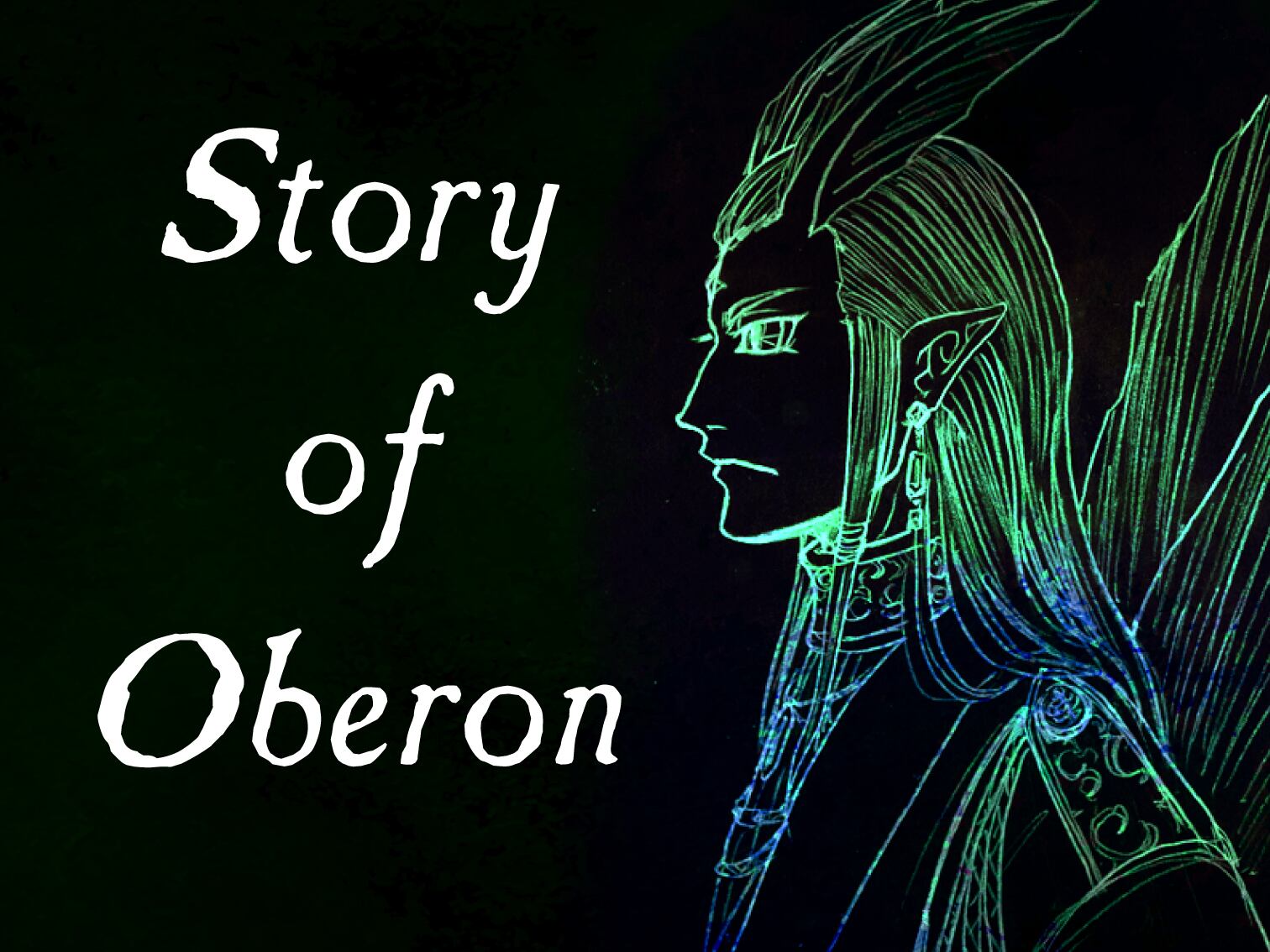

No.9 [理想の世界]
¥999
SOLD OUT
私は妖精の王、オベロン。
人間の世界でいうと何千年という時を生きているが、妖精界ではほんの数百歳だ。
今まで、人間界の様々な出来事を見つめてきた―
大きな戦争から小さな争い、
差別、比較と、偏見に自己否定…
本当に[人間]とは、わざわざ無意味な事をする、変わった生き物だと未だに思う。
―最近、妖精界に面白い人間が出入りしているとの報告を受けた。
と言っても、その事自体はとうの昔に知っている。
妖精達の間では[赤毛のアーニー]と呼ばれているらしい。
何でも、妖精界のものを人間界に広めようとしているとか……
理由は定かではないが。
私は、今の人間界の時代にしては[変わっている]であろうこの人物と会う事にした。
「いやぁ~!まさか、妖精王からお呼ばれされるとは(о´∀`о)至極光栄ですな」
従者に連れて来させたアーネストという人間は、屈託のない笑顔を浮かべ、両手を左右に広げ片足を後ろに引き姿勢を低くする、古い挨拶の仕草をした。
きっと昔の人間界の者だからだろう。
しかし見事な赤毛だ。
……あぁ、きっとあのキノコを食べたのだろうな。
よくもあんな代物を口に入れようと思ったな。
全く…
やはり相当な変わり者だ。
それについては何も指摘せず、まずはこの者が妖精界に出入りするようになるまでの経緯を聞いた。
―話によると、風の精シルフに連れられて、こちらに来るようになったこのアーネスト博士とやらは……
妖精界の美しさに惚れ込んで、それを人間界に伝えようとしているようだ。
そこで一つ疑問が湧く。
「……何故そのような事を?
お前一人がこの妖精界を楽しめれば、それでよしと言えそうなものだが」
そう問うと、アーネストは先程とは違う、穏やかな笑みをこちらに向けてきた。
「私はこの世界が好きだ。そして、人間界も。
妖精界の美しさは、きっと人間の心に良い影響をもたらす。
それは人間界の平和な未来にも繋がると、私は信じている」
私を見据える、光を帯びて澄んだ澱みのない瞳が、その言葉に嘘偽りのない事を証明していた。
「……アーネスト、お前のような人間は―
久方ぶりだ」
まだこんな人間がいたとは。
私は嬉しかった。
思わず笑みが溢れる。
「ふははっ、気に入った!
お前を私の特別な場所に連れて行こう。
他の者には滅多に見せない所だ。
もし共に見せたい者がいれば連れて来なさい」
「ほほぉ!妖精王の特別な場所とは楽しみだ!
では後日、私の友人を連れてお伺いするとしましょう」
そう言って一礼し、意気揚々とアーネストは去っていった。
―その後ろ姿に、遠い昔の……人間の親友を思い出す。
「あいつはもう……
転生、したのだろうな…」
その独り言は、誰にも聞かれる事なく空へと消えた。
―後日、白夢製作所にアーネスト博士がやってきた。
目的はもちろん、先日の「妖精王の特別な場所」にノア達を同行させる為だ。
エントランスに集まった三人に、博士はざっくりと事の成り行きを話す。
初めに口を開いたのはイーユンだった。
「オベロン様直々のお誘いとは…
初めて聞きますね」
顎に手を当てて考え込んでいる。
妖精界出身の彼が驚く程、妖精王が誰かを連れて出掛けるというのは滅多に無い事のようだ。
「オベロン…?誰だそれ」
はぐれ妖精だったロカは、初めて聞く名前にキョトンとしてクエスチョンマークを浮かべている。
その様子に、人間ではあるが彼よりも妖精界に詳しい博士が、半ば呆れて答える。
「ロカ君、君も妖精ならば覚えておきたまえ。
オベロンは、妖精界の王の名だ」
「ふ~ん」
彼はあまり興味なさげで、ふぁっ、とあくびをしながら伸びをした。
「とてもありがたいお誘いですね!楽しみです」
所長は興味津々だ。
ノアも製作所の作品の材料を集める為、博士の旅に同行したり、度々妖精界に赴く事はあったが―
こんな話は初めてだったのだ。
その反応を見た博士は、やたら嬉しそうだ。
「そうだろうそうだろう!私も楽しみだよ!
君達に声を掛けて良かった(^^)
楽しい事は、分かち合う方が喜びも増すというものだ♪」
妖精王の誘いを一番楽しみにしているのは、きっとアーネスト博士だろう。
彼の目は少年のように輝いている。
「では出発しようか!」
「いっ、今からですか!?」
楽しみとはいえ、あまりにも早い展開にノアは驚く。
「善は急げだよ(^-^)/
まぁ、無理にとは言わないが」
「……私は大丈夫ですが」
そう言って、所長は助手二人を見やる。
「所長が今すぐ行かれるのでしたら、僕はお供をするまでです」
イーユンは胸に手を当てて、ニコリと微笑んだ。
「…俺もだ」
ぶっきらぼうに答えるロカも、イーユンと同意見のようだ。
三人の同意を得た博士は、満面の笑みを浮かべて両手を腰に当てた。
「ははっ、決まりだな!
それではシルフ、頼む!」
すると、博士の側に光るものが現れた。
風の精シルフだ。
「はいはい、いつものね」
彼女は慣れた様子で答え瞬いた。
風の渦が四人を取り巻き、周囲の景色が変わってゆく。
風が収まると、そこは妖精王の御前だった。
「……アーネスト。
妖精界に来る時は、いつもシルフの力を借りているのか?」
オベロンの第一声は意外な一言だった。
「えっ…あ、いやぁ……」
何故か歯切れの悪い博士。
そこでシルフがずいっと前に出て訴える。
「そうなのよオベロン様!
この人、妖精使いが荒くて困っちゃうの」
それを聞いた妖精王は、ふぅっ、とため息をついて言った。
「アーネストよ、あまりシルフに負担を掛けないでやってくれ。
あれはかなりの生命エネルギーを消耗するからな。
私達妖精は、その消耗が大き過ぎると死ぬ事もあるのだ。
……お前は、妖精界に来るもう一つの方法も知っているのだろう?」
アーネストは額に汗を浮かべていた。
「確かに知ってはいるが…
あの方法でこちらに来るのはなかなか骨が折れ『言い訳は無用』
やはり妖精の長だけあって身内は大事なようだ。
オベロンにジロリと睨まれ、珍しく萎縮し苦笑いをする博士。
「す、すまん……
極力シルフの力は借りないようにするよ」
「うむ。ならば良いのだ」
オベロンは先程とは打って変わって、穏やかな表情になった。
「では、私の特別な場所に連れて行こう」
妖精王が片手を高く上げると、四人は再び風の渦に包まれた。
着いた先は、真っ暗な場所だった。
博士と共にいるシルフの光と、ポツリポツリと点在して光る[何か]が、かろうじて周りの輪郭を浮かび上がらせている。
どうやら洞窟のようだ。
ひんやりと冷たい空気が流れている。
息づかいさえ聞こえそうな程の静寂に包まれ、何処か遠くの方で、ポタリ、ポタリ、と水滴が滴る音が聞こえる。
低い天井から鍾乳石が伸びており、それにぶつかったロカが「痛っ」と漏らす。
「……これは、アストライトですね」
しゃがみ込み、その光る[何か]を間近で確認したノアが言った。
「その通りだ。
……付いて来なさい」
彼らは色とりどりのアストライトに朧気に照らされた狭い通路を、奥へと進んでいった。
少し行くと、四人は空気の流れと反響する音が変わるのが分かった。
どうやらこの先は開けた場所のようだ。
「わぁ……っ!」
思わず声を上げる所長。
通路を抜けると、そこは想像よりも遥かに大きな空間だった。
天井は高く、奥が見えない程広い。
しかし―
彼らを驚かせたのは違う理由だ。
そこには、見渡す限り無数のアストライトが、上から下まで、星屑を溢したように光り輝いていた。
まるで星空の中に浮いているような錯覚に陥る。
「何て……美しいんだ」
「圧巻ですね…」
「……すごいな」
四人は、その幻想的な光景にただただ立ち尽くす。
その反応を見たオベロンは、至極ご満悦の様子だ。
「視えない者には、普通の鉱石がたくさんある洞窟にしか見えないが…
視える者には、星空が一面に広がり宇宙の真っ只中にいるように見える。
よって、ここは[星の洞窟]と呼ばれている」
オベロンは目を細め、その景色を楽しそうに眺めて続けた。
「私が人間界で一番好きな場所だ。
このような所が、妖精界にもあれば良いのだが」
妖精王はこの[星の洞窟]がいたくお気に入りのようで、妖精の職人達にとても小さなアストライトの結晶などを集めさせ、この洞窟の一部を模した標本箱を作らせた程だ。
当の職人達は大変だったようだが…
―しばらくの間その景色を堪能した後、妖精王と四人は風の渦に包まれ、再び妖精界に戻った。
「とても素敵でした!ありがとうございます」
余程楽しかったのだろう。
ノアは満面の笑みを浮かべている。
その様子に、オベロンは一つ大きく頷く。
「まさか、あんな所があるとは…」
世界中を旅するアーネスト博士ですら、星の洞窟の存在を知らなかったようで、腕組みをして考え込んでいる。
「私や裏市場に関わる人間の一部しか、あの場所は知らぬ。
素晴らしい景色を守る為、秘密にしているのだよ」
先程見に行ったばかりだと言うのに、オベロンは手元の[星の洞窟]の標本箱を覗き見ている。
と、標本箱から目を離し、彼はアーネストを見た。
「お前達のような人間がいるのは、私達妖精にとって喜ばしい事だ。
……大昔の人間達は、我々のような存在との交流が当たり前にできていた。
正直、その方が私達も楽しいし、居心地がいいのだよ。
しかしそれも今は、ほんの一部の人間だけに限られている」
妖精王は四人を静かに見据える。
「この[妖精界]と[人間界]は少なからず相互作用があり、人間達の思念の影響を受ける。
それ故―
この世界は、昔ほど人間に認知されなくなった分……世界が希薄になりつつある。
それは、我々妖精にとって由々しき事態だ」
そこで彼は、ふっ、と優しく微笑んだ。
「私達妖精も望んでいるのだよ。
妖精界と共存していける…
本当の意味で平和な、新しい人間界というものを」
一呼吸置いてオベロンは続けた。
「だが、私達のような者や、このような世界が存在する事を、人間たちに知られては困ると思っている者達も昔から存在する。
それは秘密結社という形であったり、個人の場合もあり、人間だったりそうでない者であったり……様々だがな」
その理由について大方の予想はついていた博士だったが、あえて問う。
「何故知られては困るのだ?」
妙な沈黙の後、オベロンは答えた。
「それによって、皆が人間界の仕組みのカラクリ―
自分の中にある無限の創造性、可能性に気付き、人間界を影で支配する者達の思い通りに動かしづらくなるからだ。
つまり……
アーネスト、お前のような活動をする存在は、彼らからするととても目障りのはずだ。
よって、あまり派手に動き回ると命の危険すらある。
………気を付けなさい」
博士は常若の国―妖精界の力によって若返っているとはいえ、不死ではない。
人間界に居続ければ、再び歳を取り身体は衰えていくし、肉体に深刻なダメージを受ければ、普通の人間のように命を落とすだろう。
博士はその忠告の意味を知った上で、いつもの笑みを見せた。
「ならば尚更、私はまだあちらに旅立つわけにはいかないな。
人間界は、私やあなたが目指す世界にはまだまだ程遠い。
しかし……
私には、私の意思を継いでくれる親友達がいる。
万が一、私が人間としての生を終えても…
彼らに後を任せる事ができるから、悔いは無いよ」
そう言ってアーネストは、ノア、イーユン、ロカの三人それぞれに視線を送った。
「博士……」
ノアは複雑な面持ちで、その視線を受ける。
重い沈黙を破るように、博士はオベロンに向かってニカッと人懐こい笑顔を向けた。
「この生を終えたら、次は妖精にでも生まれ変わろうかな!」
「………それは止めてくれ」
そうは言いつつも、彼の申し出に妖精王はまんざらでもなさそうだ。
楽しそうに笑い合う四人を見ながら、彼は思う。
こんな人間達がいるのなら……
人間界も、まだまだこれからどうなるか楽しみだ。
(…………お前も、何処かで見守っていてくれ。
それぞれの世界の行く末を)
微笑みを浮かべた彼は、月が現れた彼方の空を見つめ―
今は無き親友に、心の中でそっと語り掛けたのだった。


![No.1 [人生は白昼夢] No.1 [人生は白昼夢]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/c1308c02e5031ea9ba33524569aaab4e.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
![No.2 [星の種] No.2 [星の種]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/5890b1cd264f717cea10d2560a85e612.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
