No.6 [未知なる世界]
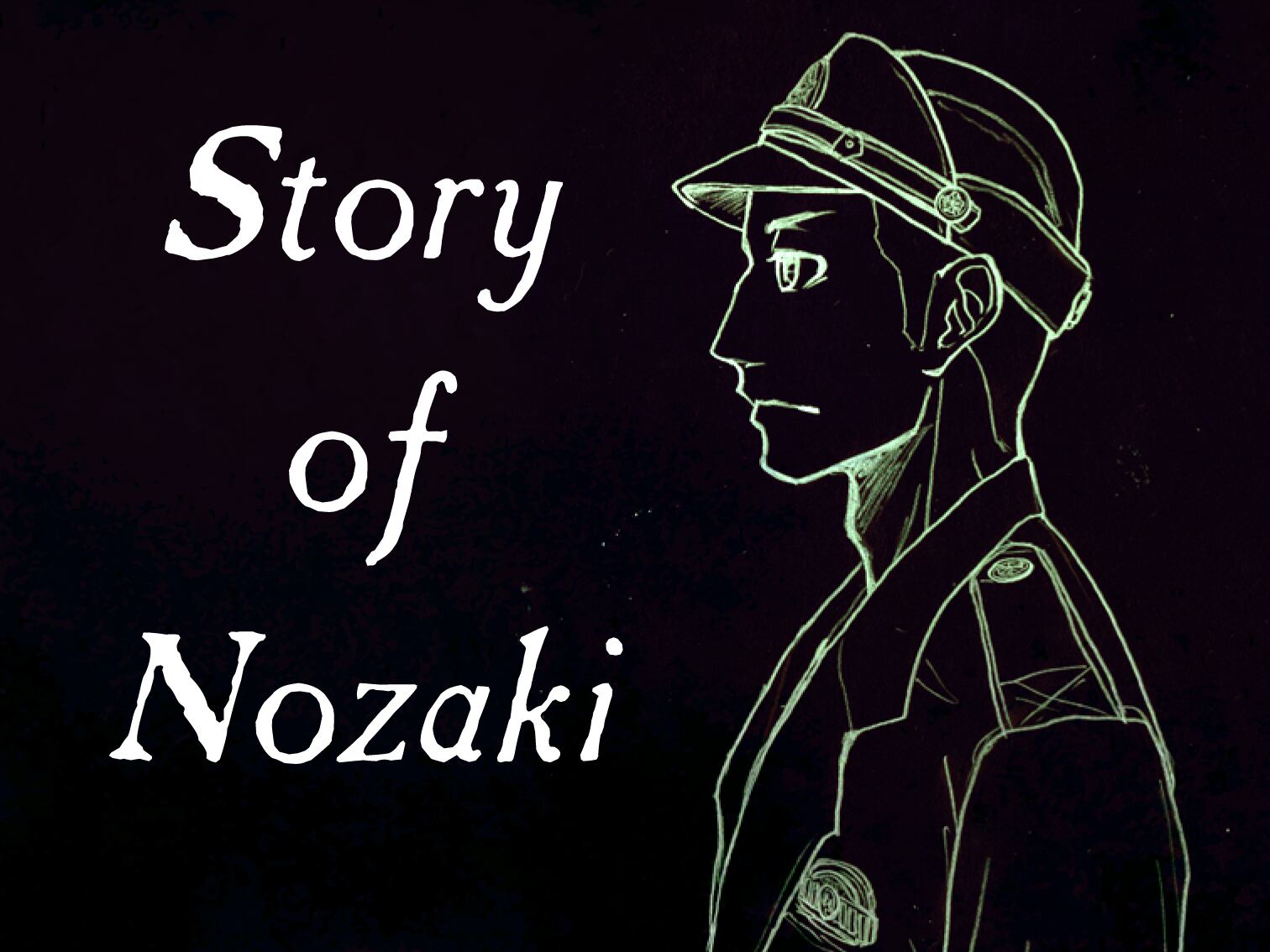

No.6 [未知なる世界]
¥666
SOLD OUT
別に子供の頃から警察官になりたかったわけじゃない。
ただ、仕事を探していただけだった。
それまで別の職場―
牧場で働いていた俺は、馬がとても好きだった。
辛い時ももちろんあったが、毎日が楽しくて充実していた。
訳あって転職する事になり、「警察官募集!」の張り紙を見て面接を受けた。
採用された。
ただそれだけ。
この仕事はよく毛嫌いされる。
ニュースで取り上げられる一部の警察官を見て、すべてを知ったつもりの奴等に、やれ「税金泥棒」だの「嫌味な仕事だな」だの、好き放題言われるが……
ちゃんと真面目に頑張って働いてる奴がほとんどだ。
これはどんな仕事だってそう言える。
真面目に働いている奴もいれば、適当な奴も、悪い事をする奴もいる。
職業で人の良し悪しが決まるんじゃない。
最終的には個々の[人間力]だと、俺は思う。
「はぁ……」
今日も出勤前からため息ばかり出る。
憂鬱。
それ以外の何物でもない。
しかし自分で選んだ仕事だ。
誰にも文句は言えないと分かっている。
分かってはいるが……
「ダっる………」
思わず本音が口をついて出る。
泊まりがけ、寝ずの激務で疲れ果てた身体を引き摺るようにして、本署に向かう。
「ノザキ部長、おはようございます」
「おはよう」
今俺は[巡査部長]という立場になり、若手だった頃よりはヘコヘコしなくて済むようになったが、警察学校や入署したての頃は、本当に大変だった……
いろいろと。
まぁ、大変なのは他の仕事も一緒だが。
ロッカールームで着替えを済ませ、朝礼に出る。
それが終わったら装備品を身に付け、自分の勤務する交番へと向かう。
いつもの流れだ。
その日も交通事故などいろいろな事があり、書類作成などしているうち、夜になった。
「(そろそろパトロール行くか)」
俺は単車に乗り、管轄の地区の見回りに出た。
―しばらく走っていると、薄暗い歩道を歩く、一人の人物が目に留まった。
十代後半から二十代前半と思われる青年。
手元の紙切れを見ながら、何やらキョロキョロと周りを警戒している。
俺は単車を端に止め、この不審人物を職務質問する事にしてみた。
「どうしたんだ、そんなにキョロキョロして」
「っ!べ、別に……」
一言話しかけただけなのに、かなりおどおどしている。
額には大量の汗。
……怪しすぎる。
「荷物検査させてもらっていい?」
「…カ、カバンの中まで見なくても………」
明らかに挙動不審だ。
こいつ、薬でも持ってるんじゃないか。
しかし荷物検査はあくまでも任意の為、俺は説得する事にした。
「何か見られたら困るもんでも入ってるの?」
「入ってない、です」
「じゃあ別にいいだろう」
「………………」
と、そいつは突然走って逃げ出そうとした。
反射的にそいつの背負っているリュックを掴む。
「あっ!!」
と、何かが転がり落ちた。
リュックのサイドジッパーが少し開いていたようだ。
転がり落ちた物を拾い上げる。
「……何だこれ。光ってる?」
それは、天然石の形をしていた。
光っている。
電池で光っているのだろう、と裏返すが、蓋が無い。
「かっ、返してっ!」
そいつは俺の手からそれをむしりとった。
「オモチャなら別に見られても問題ないじゃないか」
そいつがあまりにも慌てるのを不思議に思っていると―
強い突風が吹き、いつ現れたのか分からない別の人物がすぐ側にいた。
「カンタ君~!
早速お助けが必要なようだな!」
挙動不審なこいつと違い、やけに能天気な雰囲気のやつだ。
―しかし、よく見ると……外見が異質だ。
髪は燃えるような赤、外国人だが日本語がネイティブみたいにペラペラだ。
今日はまた、変な奴によく当たるな…
そう内心げんなりしていると、その赤毛が話しかけてきた。
「私はアーネストという者だ!
よろしく(^-^)/」
握手を求めてくる。
反射的にそれを握り返してしまった。
「ど、どうも…」
一体何なんだこいつらは。
「説明しても分からないと思うから、とりあえず私達と一緒に来てもらおう」
「……?」
何処に?と、聞こうとした瞬間、俺達三人は風の渦に包まれた。
「た、竜巻か!?」
吹き飛ばされるかと思い身構えていたが、それは起こらなかった。
代わりに、辺りの景色が一変していた。
…………何処だ、ここは。
何かのマジックか?
それとも薬を嗅がされたか。
様々な可能性を考えてみる。
しかし、リアル過ぎやしないか。
「驚いたかね~!
ここは[妖精の国]だよ(^^)」
「…………………………は?」
何言ってんだこいつは。
いよいよ本当にヤバい奴だ。
そう思うしかなかった。
―すると、先程とは全く違う真剣な眼差しで、赤毛の奴がこちらを見た。
「君。
[今]目の前で実際起こっている事を、素直に感じるんだ。
そして、不思議な事を目の当たりにした時「こんな事はあり得ない」と思うように、洗脳されている事に気付きたまえ。
人は皆、無限の経験の可能性を持っているのだよ!」
……何やらよく分からない事を言っているが、周りの風景がマジックにしてはよく出来すぎている。
それに、俺は冷静な状態だった。
薬でもないらしい。
「………………」
それでも、非現実的な事態を受け入れられない。
その時、目の前に光るものが突然現れた。
「デカいホタル…?」
俺がそれを捕まえようとすると、あろう事かその光が言葉を発した。
「やめてよ!
初対面の妖精を捕まえようとするなんて失礼ね!」
怒っている。
「………………」
俺はその喋る光を無視した。
と、今度は光から大きなため息が聞こえた。
「アーネスト博士も頑固だったけど、あなたも相当頑固ね。
人間界の教育にしっかり[洗脳]されてる感じ」
「まぁ、仕方ないわね」と言う光は、外国人がやるような、両手の平を上に向けて肩をすくませるポーズを取っているような雰囲気だ。
何が何だかよく分からないが、目の前で起こっているこれが[現実]なんじゃないかと、だんだん思えてきた。
俺もおかしくなったのか。
[博士]と呼ばれた赤毛の奴が、ヘラっと笑った。
「……無理はない。
すぐに「信じろ!」などと強制はしないよ。
それよりもまずは、何故君をここに連れてきたか説明しよう」
それが俺の知りたい事だ。
「先程君が手にした、光る石を覚えているかね?」
「あぁ」
「あれは、電池や機械で光っているのではなく……あの鉱石自体が、光を放っている」
「よく聞く夜光とか蛍光性の事か?」
「……いや、あれは人によっては、光っているようには見えないのだよ」
「……??」
話が見えてこない。
「―つまり、あの石が光っているのが[視える]人間と[視えない]人間がいて、君は[視える]人間だという事だ。」
「……で?」
「ははは、君は偉く冷静だね。感心するよ」
博士とやらは何だか楽しそうだ。
すると、先程の挙動不審な奴を自分の隣に引き寄せた。
「彼は[運び屋]の新入りで、カンタ君だ。
君と同じ日本人だよ」
カンタはおどおどしている。
「………それは見たら分かる。
それで、その[運び屋]ってのは何なんだ?」
「まぁそう急かさんでくれたまえ」
「……………」
俺はイラついた。
こっちは勤務中なんだ。
話を聞いてとっとと仕事に戻らなければ。
「…[運び屋]は、先程のようなものを秘密裏に運ぶ存在だよ。
ちなみに、あの光る石は裏市場で[アストライト]と呼ばれている。
何故秘密裏に運ぶのかと言うとだね……
運び屋が運ぶ品々は、一般の市場のものとは違う、特殊な品だからなのだ」
「何でそれを裏市場で販売する必要があるんだ?」
職業柄、何となく尋問のようになってきた。
「[視えない]人間には、普通の天然石にしか見えないからね。
[視える]人間にしか、これらの価値の違いは分からない。
裏市場は、その価値を分かっている者達が集う市場だ。
よって、君のような[視える]人間が運び屋であれば、選別も任せられて安心なのだよ」
そこで博士は、肩を組んでずいっと近付いてきた。
「よって、君を[運び屋]にスカウトしようとここに連れてきた訳だ!」
今まで[幽霊]やら何やらのものを一度も視た事もなく、そんな世界とは全く無縁の場所で生きてきた自分が、何故今更そういうものが[視える]ようになったのか、不思議だった。
「きっと、今までその能力に気付くきっかけがなかったんでしょうね」
俺の考えを見透かしたかのように、喋る光が答えた。
「そうだ!
君、名前は?」
「……ノザキ」
「そうかそうか!
では、ノザキ君と呼ばせてもらうよ(^^)」
博士は改まって俺の方に向き直った。
「それで、返事はどうかな?
何も強制はしないよ。君の意志を尊重する。
しかし、[運び屋]を通して体験する事は、君にとってきっと大切な財産となる」
俺は、一呼吸置いて決意した。
「………こんな世界見せられて、今更後に引けないだろ。
[運び屋]、やらせてくれ」
「そうか!
良かった良かった!
仲間が増えてくれて嬉しいなぁo(^o^)o」
博士がはしゃぐ横で、カンタが小さな声で呟いた。
「僕、運び屋……務まるでしょうか………」
そんな自信なさげな彼の肩に手を置き、博士は力強く宣言した。
「大丈夫!
すべてはなるようになる!
若者諸君、人生まだまだこれからだ!
未来を楽しみにしたまえ(^-^)/」
[若者諸君]って……
あんた俺とそんなに歳変わんないだろ、と、博士の本当の年齢を知らないノザキは思った。
そうして、俺は表向きは警察官、裏で[運び屋]という顔を持つ事になった。
―後日、博士に連れられ再び妖精界を訪れると、ある存在を紹介された。
「君が馬に乗れると聞いたのでな、ノザキ君にピッタリのパートナーを紹介しよう!
妖精馬のグラシュティンだ」
博士がそう言って影から現れたその馬は、まさに[漆黒]というに相応しい、深い黒をしていた。
目は赤く光っている。
博士がニカッと笑った。
「仲良くしてくれたまえ~」
そう言われ、俺は馬に近付く。
「俺はグラシュティン。よろしくな」
「!」
馬が喋った。
この世界のものは何でも喋るのか。
「ちなみに、彼は馬から人間の姿にもなれるぞ」
「今変身して見せようか?」
「…………」
別に馬のままでいいのだが。
「運び屋として移動する時は彼に乗るといい」
博士はグラシュティンを見つめて言った。
ふと疑問が沸き起こる。
「……あの風の渦で移動する方法は使えないのか?」
「あ~、あれはだね……
あまり頻繁に使ってはいけない移動手段なのだよ。
詳しく話すと長くなるのだが……」
「ならいい」
「分かってくれて良かった。
では、早速仕事を頼む!」
博士は、ハガキサイズ程の小さな銀色のケースを開け、中を見せてきた。
何かの欠片がたくさん入っている。
「……これは?」
「[物語の欠片]と呼ばれていてな。
運び先の[エル・ファロ]という店の女店主がこれを手にすると、持ち主の昔の記憶を読み取れるそうだ」
「ふ~ん……?」
よく分からないが、とにかく運ぶのが俺の役目だ。
受け取った物をバッグの中に緩衝材と共に入れ、ベルトで固定した。
「これが地図だ。
港町の高台にあるのだが、この店は真夜中にしか開いていないから、注意したまえ!
もし分からなくても彼…グラシュティンが場所を知っているので、大丈夫だ」
「………」
地図を受け取る。
何とか分かりそうだ。
「では、初仕事、頑張りたまえ!」
博士の激励に、俺は頷いて見せた。
「行くぞ、グラシュティン」
「あぁ」
風を切り空を飛ぶように駆ける馬に乗り―
俺は、運び屋としての人生をスタートさせたのだった。
ただ、仕事を探していただけだった。
それまで別の職場―
牧場で働いていた俺は、馬がとても好きだった。
辛い時ももちろんあったが、毎日が楽しくて充実していた。
訳あって転職する事になり、「警察官募集!」の張り紙を見て面接を受けた。
採用された。
ただそれだけ。
この仕事はよく毛嫌いされる。
ニュースで取り上げられる一部の警察官を見て、すべてを知ったつもりの奴等に、やれ「税金泥棒」だの「嫌味な仕事だな」だの、好き放題言われるが……
ちゃんと真面目に頑張って働いてる奴がほとんどだ。
これはどんな仕事だってそう言える。
真面目に働いている奴もいれば、適当な奴も、悪い事をする奴もいる。
職業で人の良し悪しが決まるんじゃない。
最終的には個々の[人間力]だと、俺は思う。
「はぁ……」
今日も出勤前からため息ばかり出る。
憂鬱。
それ以外の何物でもない。
しかし自分で選んだ仕事だ。
誰にも文句は言えないと分かっている。
分かってはいるが……
「ダっる………」
思わず本音が口をついて出る。
泊まりがけ、寝ずの激務で疲れ果てた身体を引き摺るようにして、本署に向かう。
「ノザキ部長、おはようございます」
「おはよう」
今俺は[巡査部長]という立場になり、若手だった頃よりはヘコヘコしなくて済むようになったが、警察学校や入署したての頃は、本当に大変だった……
いろいろと。
まぁ、大変なのは他の仕事も一緒だが。
ロッカールームで着替えを済ませ、朝礼に出る。
それが終わったら装備品を身に付け、自分の勤務する交番へと向かう。
いつもの流れだ。
その日も交通事故などいろいろな事があり、書類作成などしているうち、夜になった。
「(そろそろパトロール行くか)」
俺は単車に乗り、管轄の地区の見回りに出た。
―しばらく走っていると、薄暗い歩道を歩く、一人の人物が目に留まった。
十代後半から二十代前半と思われる青年。
手元の紙切れを見ながら、何やらキョロキョロと周りを警戒している。
俺は単車を端に止め、この不審人物を職務質問する事にしてみた。
「どうしたんだ、そんなにキョロキョロして」
「っ!べ、別に……」
一言話しかけただけなのに、かなりおどおどしている。
額には大量の汗。
……怪しすぎる。
「荷物検査させてもらっていい?」
「…カ、カバンの中まで見なくても………」
明らかに挙動不審だ。
こいつ、薬でも持ってるんじゃないか。
しかし荷物検査はあくまでも任意の為、俺は説得する事にした。
「何か見られたら困るもんでも入ってるの?」
「入ってない、です」
「じゃあ別にいいだろう」
「………………」
と、そいつは突然走って逃げ出そうとした。
反射的にそいつの背負っているリュックを掴む。
「あっ!!」
と、何かが転がり落ちた。
リュックのサイドジッパーが少し開いていたようだ。
転がり落ちた物を拾い上げる。
「……何だこれ。光ってる?」
それは、天然石の形をしていた。
光っている。
電池で光っているのだろう、と裏返すが、蓋が無い。
「かっ、返してっ!」
そいつは俺の手からそれをむしりとった。
「オモチャなら別に見られても問題ないじゃないか」
そいつがあまりにも慌てるのを不思議に思っていると―
強い突風が吹き、いつ現れたのか分からない別の人物がすぐ側にいた。
「カンタ君~!
早速お助けが必要なようだな!」
挙動不審なこいつと違い、やけに能天気な雰囲気のやつだ。
―しかし、よく見ると……外見が異質だ。
髪は燃えるような赤、外国人だが日本語がネイティブみたいにペラペラだ。
今日はまた、変な奴によく当たるな…
そう内心げんなりしていると、その赤毛が話しかけてきた。
「私はアーネストという者だ!
よろしく(^-^)/」
握手を求めてくる。
反射的にそれを握り返してしまった。
「ど、どうも…」
一体何なんだこいつらは。
「説明しても分からないと思うから、とりあえず私達と一緒に来てもらおう」
「……?」
何処に?と、聞こうとした瞬間、俺達三人は風の渦に包まれた。
「た、竜巻か!?」
吹き飛ばされるかと思い身構えていたが、それは起こらなかった。
代わりに、辺りの景色が一変していた。
…………何処だ、ここは。
何かのマジックか?
それとも薬を嗅がされたか。
様々な可能性を考えてみる。
しかし、リアル過ぎやしないか。
「驚いたかね~!
ここは[妖精の国]だよ(^^)」
「…………………………は?」
何言ってんだこいつは。
いよいよ本当にヤバい奴だ。
そう思うしかなかった。
―すると、先程とは全く違う真剣な眼差しで、赤毛の奴がこちらを見た。
「君。
[今]目の前で実際起こっている事を、素直に感じるんだ。
そして、不思議な事を目の当たりにした時「こんな事はあり得ない」と思うように、洗脳されている事に気付きたまえ。
人は皆、無限の経験の可能性を持っているのだよ!」
……何やらよく分からない事を言っているが、周りの風景がマジックにしてはよく出来すぎている。
それに、俺は冷静な状態だった。
薬でもないらしい。
「………………」
それでも、非現実的な事態を受け入れられない。
その時、目の前に光るものが突然現れた。
「デカいホタル…?」
俺がそれを捕まえようとすると、あろう事かその光が言葉を発した。
「やめてよ!
初対面の妖精を捕まえようとするなんて失礼ね!」
怒っている。
「………………」
俺はその喋る光を無視した。
と、今度は光から大きなため息が聞こえた。
「アーネスト博士も頑固だったけど、あなたも相当頑固ね。
人間界の教育にしっかり[洗脳]されてる感じ」
「まぁ、仕方ないわね」と言う光は、外国人がやるような、両手の平を上に向けて肩をすくませるポーズを取っているような雰囲気だ。
何が何だかよく分からないが、目の前で起こっているこれが[現実]なんじゃないかと、だんだん思えてきた。
俺もおかしくなったのか。
[博士]と呼ばれた赤毛の奴が、ヘラっと笑った。
「……無理はない。
すぐに「信じろ!」などと強制はしないよ。
それよりもまずは、何故君をここに連れてきたか説明しよう」
それが俺の知りたい事だ。
「先程君が手にした、光る石を覚えているかね?」
「あぁ」
「あれは、電池や機械で光っているのではなく……あの鉱石自体が、光を放っている」
「よく聞く夜光とか蛍光性の事か?」
「……いや、あれは人によっては、光っているようには見えないのだよ」
「……??」
話が見えてこない。
「―つまり、あの石が光っているのが[視える]人間と[視えない]人間がいて、君は[視える]人間だという事だ。」
「……で?」
「ははは、君は偉く冷静だね。感心するよ」
博士とやらは何だか楽しそうだ。
すると、先程の挙動不審な奴を自分の隣に引き寄せた。
「彼は[運び屋]の新入りで、カンタ君だ。
君と同じ日本人だよ」
カンタはおどおどしている。
「………それは見たら分かる。
それで、その[運び屋]ってのは何なんだ?」
「まぁそう急かさんでくれたまえ」
「……………」
俺はイラついた。
こっちは勤務中なんだ。
話を聞いてとっとと仕事に戻らなければ。
「…[運び屋]は、先程のようなものを秘密裏に運ぶ存在だよ。
ちなみに、あの光る石は裏市場で[アストライト]と呼ばれている。
何故秘密裏に運ぶのかと言うとだね……
運び屋が運ぶ品々は、一般の市場のものとは違う、特殊な品だからなのだ」
「何でそれを裏市場で販売する必要があるんだ?」
職業柄、何となく尋問のようになってきた。
「[視えない]人間には、普通の天然石にしか見えないからね。
[視える]人間にしか、これらの価値の違いは分からない。
裏市場は、その価値を分かっている者達が集う市場だ。
よって、君のような[視える]人間が運び屋であれば、選別も任せられて安心なのだよ」
そこで博士は、肩を組んでずいっと近付いてきた。
「よって、君を[運び屋]にスカウトしようとここに連れてきた訳だ!」
今まで[幽霊]やら何やらのものを一度も視た事もなく、そんな世界とは全く無縁の場所で生きてきた自分が、何故今更そういうものが[視える]ようになったのか、不思議だった。
「きっと、今までその能力に気付くきっかけがなかったんでしょうね」
俺の考えを見透かしたかのように、喋る光が答えた。
「そうだ!
君、名前は?」
「……ノザキ」
「そうかそうか!
では、ノザキ君と呼ばせてもらうよ(^^)」
博士は改まって俺の方に向き直った。
「それで、返事はどうかな?
何も強制はしないよ。君の意志を尊重する。
しかし、[運び屋]を通して体験する事は、君にとってきっと大切な財産となる」
俺は、一呼吸置いて決意した。
「………こんな世界見せられて、今更後に引けないだろ。
[運び屋]、やらせてくれ」
「そうか!
良かった良かった!
仲間が増えてくれて嬉しいなぁo(^o^)o」
博士がはしゃぐ横で、カンタが小さな声で呟いた。
「僕、運び屋……務まるでしょうか………」
そんな自信なさげな彼の肩に手を置き、博士は力強く宣言した。
「大丈夫!
すべてはなるようになる!
若者諸君、人生まだまだこれからだ!
未来を楽しみにしたまえ(^-^)/」
[若者諸君]って……
あんた俺とそんなに歳変わんないだろ、と、博士の本当の年齢を知らないノザキは思った。
そうして、俺は表向きは警察官、裏で[運び屋]という顔を持つ事になった。
―後日、博士に連れられ再び妖精界を訪れると、ある存在を紹介された。
「君が馬に乗れると聞いたのでな、ノザキ君にピッタリのパートナーを紹介しよう!
妖精馬のグラシュティンだ」
博士がそう言って影から現れたその馬は、まさに[漆黒]というに相応しい、深い黒をしていた。
目は赤く光っている。
博士がニカッと笑った。
「仲良くしてくれたまえ~」
そう言われ、俺は馬に近付く。
「俺はグラシュティン。よろしくな」
「!」
馬が喋った。
この世界のものは何でも喋るのか。
「ちなみに、彼は馬から人間の姿にもなれるぞ」
「今変身して見せようか?」
「…………」
別に馬のままでいいのだが。
「運び屋として移動する時は彼に乗るといい」
博士はグラシュティンを見つめて言った。
ふと疑問が沸き起こる。
「……あの風の渦で移動する方法は使えないのか?」
「あ~、あれはだね……
あまり頻繁に使ってはいけない移動手段なのだよ。
詳しく話すと長くなるのだが……」
「ならいい」
「分かってくれて良かった。
では、早速仕事を頼む!」
博士は、ハガキサイズ程の小さな銀色のケースを開け、中を見せてきた。
何かの欠片がたくさん入っている。
「……これは?」
「[物語の欠片]と呼ばれていてな。
運び先の[エル・ファロ]という店の女店主がこれを手にすると、持ち主の昔の記憶を読み取れるそうだ」
「ふ~ん……?」
よく分からないが、とにかく運ぶのが俺の役目だ。
受け取った物をバッグの中に緩衝材と共に入れ、ベルトで固定した。
「これが地図だ。
港町の高台にあるのだが、この店は真夜中にしか開いていないから、注意したまえ!
もし分からなくても彼…グラシュティンが場所を知っているので、大丈夫だ」
「………」
地図を受け取る。
何とか分かりそうだ。
「では、初仕事、頑張りたまえ!」
博士の激励に、俺は頷いて見せた。
「行くぞ、グラシュティン」
「あぁ」
風を切り空を飛ぶように駆ける馬に乗り―
俺は、運び屋としての人生をスタートさせたのだった。


![No.1 [人生は白昼夢] No.1 [人生は白昼夢]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/c1308c02e5031ea9ba33524569aaab4e.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
![No.2 [星の種] No.2 [星の種]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/5890b1cd264f717cea10d2560a85e612.jpg?imformat=generic&q=90&im=Resize,width=640,type=normal)
